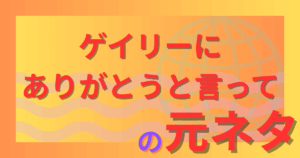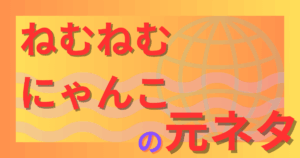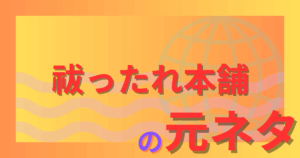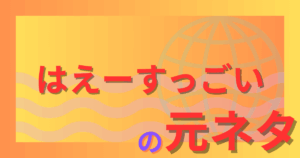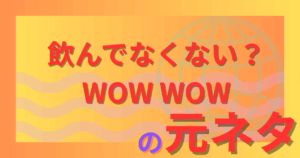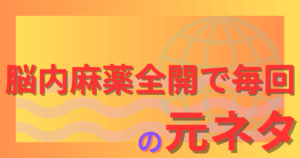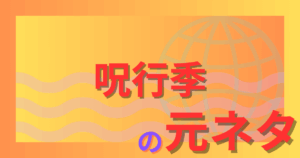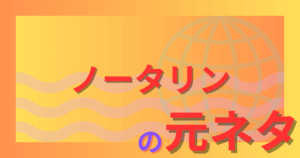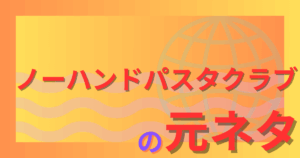インターネットの世界では数え切れないほどのミームが誕生してきましたが、その中でも特に長く愛されているのが「宇宙猫」です。驚いた表情の猫と壮大な宇宙の背景を組み合わせた不思議なコラージュは、見る人に強烈なインパクトを与え、理解不能な状況を表す象徴的な画像として広まりました。では、この宇宙猫の元ネタは一体どこから生まれたのでしょうか。海外での起源から日本での流行、そして誤解されがちなフェリセットとの違いまで、詳しく見ていきましょう。
この記事では、宇宙猫の元ネタや起源、ネットでの広まり方を徹底解説します。
宇宙猫の元ネタとは?起源と誕生の背景
- 宇宙猫の元ネタの起源とは?
- いつ頃から流行った?
- 海外での広まりと初期の事例
宇宙猫の元ネタの起源とは?
「宇宙猫」とは、猫の驚いた顔や目を見開いた表情を、星雲や銀河の宇宙背景に合成したコラージュ画像を指します。起源をたどると、2006年の海外ネット文化にたどり着きます。この頃、音楽ブログ「MatrixSynth」に投稿された「Space ARP」という画像や、YTMND(You’re The Man Now Dog)という掲示板文化で登場した「Cat on a Keyboard in Space」と呼ばれるコラージュが話題となりました。これらが「宇宙+猫」のテンプレを定着させ、現在の宇宙猫ミームにつながったとされています。
いつ頃から流行った?
海外で最初に流行したのは2006年頃ですが、日本で「宇宙猫」という呼び名が定着したのは2014年頃です。Twitterやまとめサイトを中心に、「理解不能なことに直面したときの気持ちを代弁する画像」として使われ、急速に広まりました。単なるコラージュではなく、日常会話の中で「宇宙猫状態」として使われるようになった点が、日本独自の広まり方といえます。
海外での広まりと初期の事例
海外では「SpaceCat」「GalaxyCat」というタグが早い時期から存在していました。猫はインターネット文化の中心的存在であり、Nyan Catなどの“宇宙で活躍する猫”系のミームが数多く生まれています。宇宙猫もその流れを汲む存在で、シンプルに合成しやすく、視覚的インパクトが強いことから拡散力が高まりました。
宇宙猫の元ネタが日本で広まった理由
- 宇宙猫が「理解不能」の象徴として定着
- ミームとしての特徴と使われ方
- フェリセットとの違いとよくある誤解
宇宙猫が「理解不能」の象徴として定着
日本で宇宙猫が人気を得た大きな理由は、その表情にあります。猫の真剣で不思議そうな顔と、無限に広がる宇宙の背景が合わさることで、**「理解が追いつかない」「頭が真っ白になる」**といった感情を的確に表す画像になりました。そのため、ネット上では「宇宙猫顔」「宇宙猫状態」といった言葉が生まれ、ネタとしての寿命が長く保たれています。
ミームとしての特徴と使われ方
宇宙猫は単なるおもしろ画像にとどまらず、反応画像・大喜利素材として活用されます。例えば、難解なニュース、理解不能な出来事、シュールなやり取りなどに添えることで、画像一枚で状況を説明できる点が特徴です。また、Photoshopやスマホアプリで誰でも簡単に作れるため、派生画像が次々と生まれ、文化として定着しました。
フェリセットとの違いとよくある誤解
「宇宙猫」という言葉を調べると、フランスが1963年に打ち上げた実在の宇宙猫フェリセット(Félicette)と混同されることがあります。しかし、フェリセットは歴史的事実であり、ミームの元ネタではありません。宇宙猫ミームはあくまでもネットで生まれた合成画像の文化であり、実際に宇宙に行った猫とは別物です。この違いを知っておくと、誤解なく楽しめます。
宇宙猫の元ネタとは?まとめ
- 宇宙猫の元ネタは2006年の海外ネット文化で生まれた
- 日本では2014年頃から「理解不能」の象徴として広まった
- 表情と宇宙背景の組み合わせがシュールで共感を呼んだ
- 派生や二次創作が多く、長寿ミームとして定着
- 実在の宇宙猫「フェリセット」とは無関係