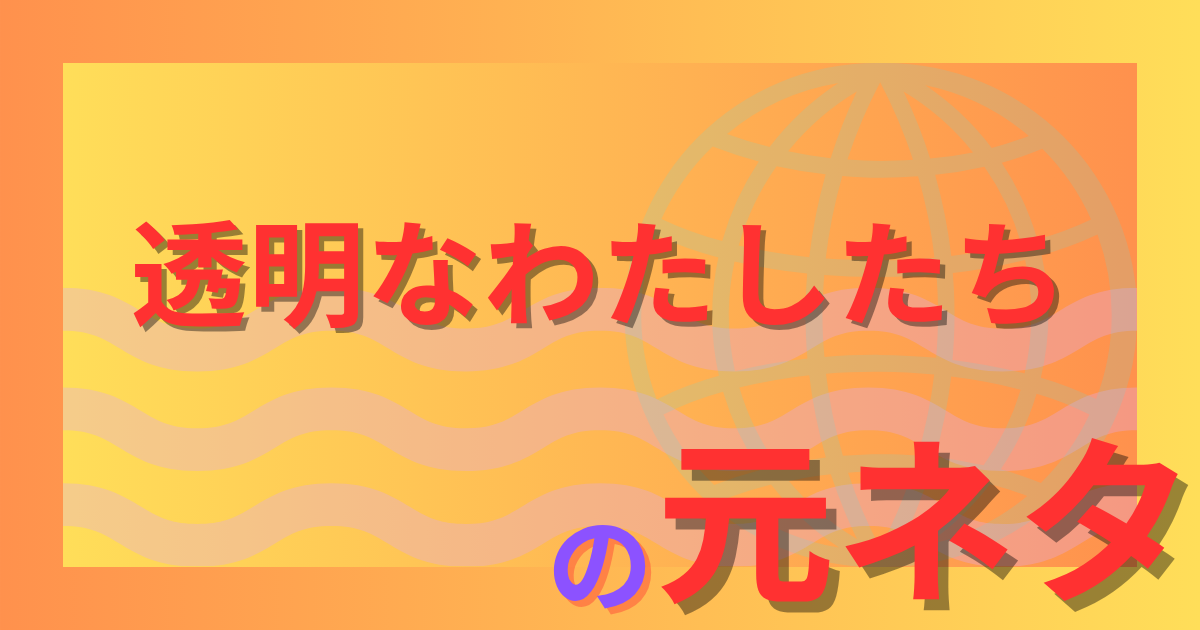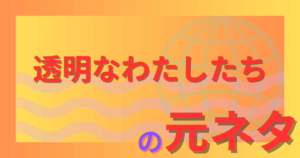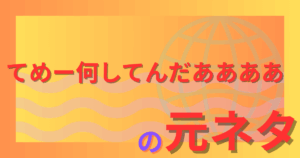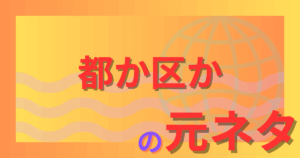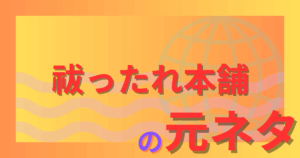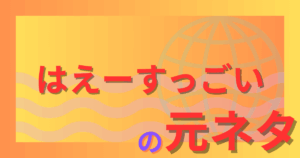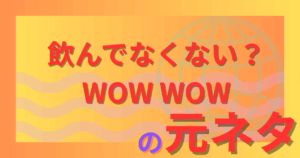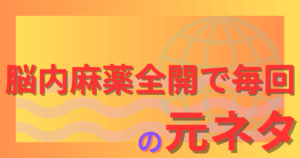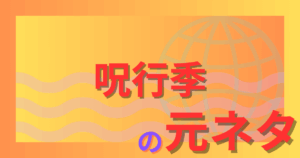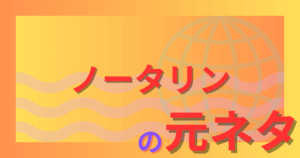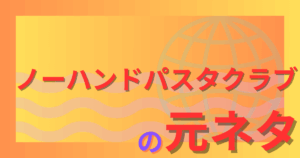現代社会の孤独や無関心を描いたドラマ「透明なわたしたち」。
物語の中で登場する放火事件や無差別刺傷事件、そして登場人物たちの“見えない心の闇”が大きな話題になっています。
視聴者の間では「このドラマは実話なの?」「元ネタとなった事件があるの?」といった疑問も多く上がっています。
この記事では、「透明なわたしたち」の元ネタの有無や、登場人物の抱える闇、そして作品に込められた社会的メッセージについて詳しく解説します。
透明なわたしたちの元ネタとは?物語の背景とテーマを解説
- 透明なわたしたちはオリジナル脚本だった
- モチーフとなった社会問題や現実とのリンク
- タイトル「透明なわたしたち」に込められた意味
透明なわたしたちはオリジナル脚本だった
ドラマ「透明なわたしたち」は、特定の事件や小説をもとにした作品ではなく、松本優作さんによるオリジナル脚本です。
2024年9月からABEMAで配信され、藤井道人さんがプロデュースを担当。
登場人物の高校時代と現在を行き来しながら、「他人の目に映らない痛み」「誰にも気づかれない存在」をテーマに描いています。
脚本家の松本優作さんは、インタビューで「現代の“見えない孤独”を描きたかった」と語っており、実話ではないものの社会問題をリアルに映し出す意図があったとされています。
モチーフとなった社会問題や現実とのリンク
元ネタは存在しないものの、現実社会の痛みを投影したフィクションであることは確かです。
SNSの誹謗中傷、若者の孤立、無差別事件など、現代日本で実際に起きているテーマが物語の随所に組み込まれています。
作中ではSNSで人を嘲笑する描写も登場し、匿名社会の冷たさを強く印象づけています。
つまり、「透明なわたしたち」は特定のモデルではなく、**“今を生きる誰もが感じうる孤独”**を描いた作品といえるでしょう。
タイトル「透明なわたしたち」に込められた意味
「透明なわたしたち」というタイトルには、存在しているのに誰にも見えない苦しみという意味が込められています。
人間関係の中で無視されたり、SNSで誰にも反応されなかったりする現代の孤独感を象徴しています。
作品全体を通して、「あなたは誰かを見ようとしているか?」という問いが投げかけられているのです。
実際の事件や登場人物の闇に見る“透明さ”の正体
- 尾関健の抱える孤独と衝動
- 放火事件と無差別刺傷事件の共通点
- SNS社会が生んだ「見られる痛み」
尾関健の抱える孤独と衝動
ドラマの中で最も強い印象を残すのが、無差別刺傷事件の犯人・尾関健です。
彼は母の死や友人からの疎外をきっかけに、自分の存在が「透明」になっていく感覚に苦しんでいました。
「見てほしい」「理解されたい」という思いが届かず、やがてそれが他者への怒りと絶望に変わっていきます。
尾関の行動は、単なる暴力ではなく、“見えないことの苦しみ”が爆発した結果とも言えます。
この描写は、社会の無関心が人をどこまで追い詰めるかを示す象徴的なシーンです。
放火事件と無差別刺傷事件の共通点
物語には、高校時代に起きた「放火事件」と、現在の「刺傷事件」が並行して登場します。
どちらの事件にも共通しているのは、周囲が見ようとしなかった現実です。
放火事件の際、誰も真実を知ろうとせず、尾関は孤立。
その“見過ごされた痛み”が、後の事件を引き起こす原因となりました。
この構成は、過去の出来事が現在に影響を及ぼす「因果の物語」としても秀逸です。
SNS社会が生んだ「見られる痛み」
一方で、見えない痛みとは対照的に、“見られることの苦しみ”も描かれています。
芸能志望だった桜井梨沙は、SNSで理想の自分を演じ続けた結果、現実とのギャップに苦しみました。
また、他人の失敗を面白がる匿名コメントや、誰かを嘲笑する風潮など、「見られる」「晒される」ことへの恐怖も強く描かれています。
つまり、この作品は「見えない人」と「見られすぎる人」の両方の苦しみを描いた、現代社会そのものの縮図といえます。
透明なわたしたちの元ネタと登場人物の闇まとめ
- 「透明なわたしたち」はオリジナル脚本で、実話や事件の元ネタは存在しない。
- SNS誹謗中傷・孤独・無関心など、現代社会のモチーフを作品に反映している。
- 尾関健を中心に、「見えない存在」になった人々の苦しみを群像劇として描く。
- “透明であること”と“見られること”という二つの痛みを通して、人間の心の闇を浮き彫りにしている。