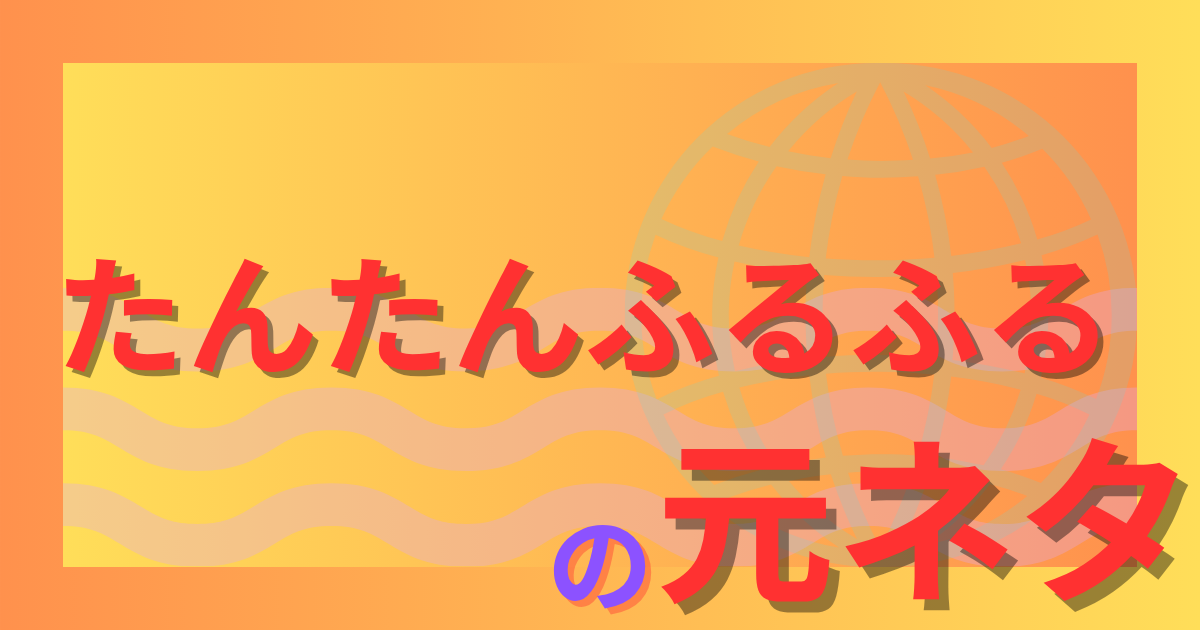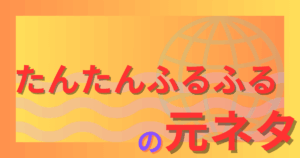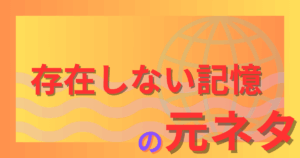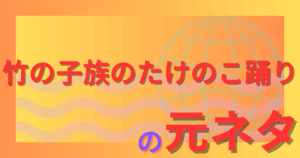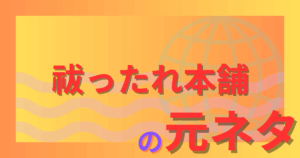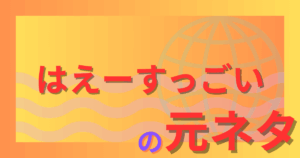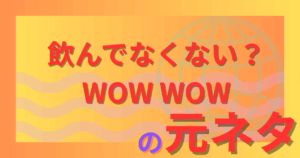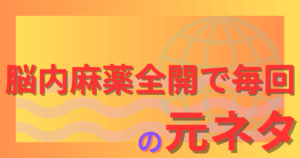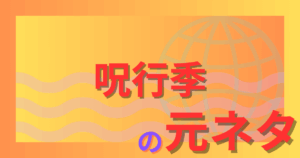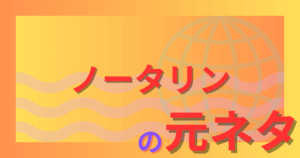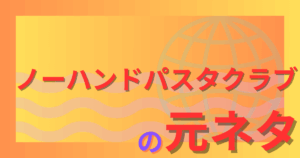近ごろSNSで耳にする「たんたんふるふる」というフレーズ。かわいらしい響きとリズミカルな音がクセになるとして、TikTokやInstagramなどで爆発的に流行しています。
しかし、この言葉の**元ネタが韓国発の楽曲「マラタンフル(Malatanghulu)」**だと知っている人は意外と少ないかもしれません。
この記事では、「たんたんふるふる」の元ネタとなった韓国曲の正体や、TikTokを中心にどのようにバズったのかをわかりやすく解説します。
たんたんふるふるの元ネタとは?流行のきっかけを解説
- たんたんふるふるの元ネタは韓国曲「マラタンフル」
- いつから流行った?TikTokで火がついた理由
たんたんふるふるの元ネタは韓国曲「マラタンフル」
「たんたんふるふる」の元ネタは、韓国の若手クリエイター SEO EVE(ソイヴ/서이브) が発表した楽曲 『마라탕후루(マラタンフル/Malatanghulu)』 です。
この曲の歌詞の中に登場する 「탕탕 후루후루(タンタン フルフル)」 というフレーズが、日本語話者にも「たんたんふるふる」として聞こえることから広まりました。
歌詞の内容は、「先輩にマラタン(麻辣湯)をおごってほしい」「フルーツ飴(タンフル)も一緒に!」という、可愛らしいお願いを表現したもの。
リズミカルで中毒性のあるフレーズが特徴で、短いワンフレーズだけでも印象に残るため、ショート動画との相性が抜群でした。
いつから流行った?TikTokで火がついた理由
この楽曲が韓国で話題になったのは 2023年頃。
発表直後から TikTokやYouTube Shortsで「マラタンフルチャレンジ」 が広まり、曲に合わせて踊る投稿が次々と拡散されました。
特に注目されたのは、SEO EVE自身が公開したキュートなダンス動画。
手を振りながら「탕탕 후루후루」と口ずさむ姿がかわいいと評判になり、子どもから大人まで真似する人が急増。
SNSの音源ランキングでも1位を獲得し、わずか数週間で「韓国で最も使われた楽曲」のひとつとなりました。
たんたんふるふるのブームと広がりを深掘り
- SEO EVE(ソイヴ)の発信と子ども世代の共感
- マラタン×タンフル文化が生んだ可愛い系ブーム
- 日本での「たんたんふるふる」表記とミーム化の流れ
SEO EVE(ソイヴ)の発信と子ども世代の共感
「たんたんふるふる」を広めたSEO EVEは、もともと韓国で活動していたキッズクリエイター出身のアーティストです。
彼女の作風はポップで明るく、誰でも口ずさめるメロディが多く、若年層に人気があります。
SNS世代の子どもたちは、難しい言葉よりも「ノリ」や「音のかわいさ」で共感する傾向があり、SEO EVEの曲はまさにそのツボを突いていました。
そのため、同世代の共感によって自然に拡散し、学校や家庭内でも口ずさまれるようになったのです。
マラタン×タンフル文化が生んだ可愛い系ブーム
曲名に登場する「マラタン(麻辣湯)」と「タンフル(果実飴)」は、どちらも韓国で人気の食べ物。
特にタンフルはSNS映えするスイーツとして流行しており、屋台やカフェで手軽に買える“映えフード”の象徴でした。
この2つを掛け合わせた「マラタンフル」というタイトルは、ユーモラスで親しみやすく、**「食べもの×かわいさ×音感」**という3つの要素が融合。
その独特の響きが、韓国だけでなく日本の若者にも刺さったと言えます。
日本での「たんたんふるふる」表記とミーム化の流れ
日本では、韓国語の「탕탕 후루후루(タンタン フルフル)」をそのまま耳コピした形で「たんたんふるふる」と呼ばれるようになりました。
TikTok上では2024年ごろから「#たんたんふるふる」タグが登場し、日本語圏のクリエイターも次々とダンスやパロディ動画を投稿。
また、音の可愛らしさから**“意味のないかわいい言葉”としてのミーム化**も進み、動画のBGMやスタンプなどにも広く使われています。
いまでは、特定の曲というより「雰囲気を表すネットスラング」に近い形で定着しつつあります。
たんたんふるふるの元ネタとは?韓国発の曲「マラタンフル」がバズった理由まとめ
- 元ネタはSEO EVEの楽曲「マラタンフル(Malatanghulu)」
- 「탕탕 후루후루(タンタンフルフル)」の音が可愛く、日本語圏で「たんたんふるふる」として広まった
- TikTokのダンスチャレンジでバズり、韓国から日本へと人気が拡大
- 韓国スイーツ文化やSNS映えトレンドも後押し
- 現在は「かわいい音の言葉」としてネットミーム化している