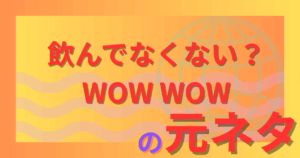三谷幸喜監督の最新作『スオミの話をしよう』は、2024年公開の話題作です。主演の長澤まさみさんを中心に、5人の元夫たちが“スオミ”という女性の謎を語り合う独特な構成が注目を集めました。
この記事では、映画のあらすじや特徴を紹介しつつ、『スオミの話をしよう』に隠された元ネタやオマージュの可能性を徹底解説します。
『スオミの話をしよう』とはどんな映画?あらすじと作品の特徴
- 公開日と基本情報
- ストーリーのあらすじ
- スオミという名前の意味(フィンランドとの関係)
公開日と基本情報
『スオミの話をしよう』は、2024年9月13日に全国公開された三谷幸喜監督のオリジナル映画です。主演は長澤まさみさんで、共演には西島秀俊さん、阿部サダヲさん、吉田羊さんら豪華キャストが勢ぞろいしています。
本作は三谷監督らしい会話劇の構成を持ちながら、ミステリーと人間ドラマの要素を融合した群像劇として高い評価を得ています。
ストーリーのあらすじ
物語の中心となるのは、謎めいた女性・スオミ。彼女は過去に5人の男性と結婚・離婚を繰り返し、ある日突然姿を消してしまいます。
残された元夫たちは彼女の消息を追いながら、それぞれが見ていた“スオミ像”を語り合っていくのです。
物語が進むにつれて、スオミが抱えていた秘密や、彼女の生き方が少しずつ浮かび上がっていきます。
スオミという名前の意味(フィンランドとの関係)
「スオミ(Suomi)」という言葉は、フィンランド語で“フィンランド”を意味する単語です。
映画ではこの名前が象徴的に使われており、静かで凛とした国のイメージが、主人公スオミのミステリアスな魅力と重なっています。
また、舞台の一部に“ヘルシンキ”が登場することから、タイトルには再生や新しい出発という意味合いも込められていると考えられます。
『スオミの話をしよう』に隠された元ネタと映画オマージュ
- 『イヴの総て(All About Eve)』との共通点
- 『サンセット大通り』との演出上の類似
- 『キサラギ』や『大豆田とわ子と三人の元夫』との構造的な共鳴
- フィンランドを象徴とするタイトルの意味
- 三谷幸喜監督が意識したであろうテーマ性
『イヴの総て(All About Eve)』との共通点
『スオミの話をしよう』の英題は**「All About Suomi」**。これは1950年の名作映画『All About Eve(イヴの総て)』を明確に意識したものと考えられます。
どちらの作品も、周囲の人々が一人の女性について語る構成を取っており、真実の姿が語りの中から少しずつ浮かび上がっていくという点で共通しています。
英題の構造そのものがオマージュ的な仕掛けになっているのです。
『サンセット大通り』との演出上の類似
もう一つの影響として指摘されているのが、1950年の映画『サンセット大通り(Sunset Boulevard)』です。
特に、屋敷や階段の使い方、“元配偶者が使用人となって仕えている”という設定などに共通点が見られます。
『スオミの話をしよう』では、この古典映画のモチーフを反転させ、登場人物たちの関係性をユーモラスかつ切なく描いています。
『キサラギ』や『大豆田とわ子と三人の元夫』との構造的な共鳴
一つの部屋に集まった複数人が“いない誰か”について語るという構成は、映画『キサラギ』を思い出させます。
また、「元夫たちが一堂に会する」という設定は、ドラマ『大豆田とわ子と三人の元夫』と表層的に似ています。
ただし、『スオミの話をしよう』はこれらを単なる模倣ではなく、会話劇とミステリーの融合として再構成しているのが特徴です。
フィンランドを象徴とするタイトルの意味
タイトルに使われた「スオミ」は、単なる名前ではなく象徴的なキーワードです。
フィンランドは「森と湖の国」と呼ばれ、静謐・孤独・再生といったイメージを持ちます。
この言葉を主人公の名前にしたことで、スオミ=静かに生まれ変わる女性という意味合いが強調されています。
三谷幸喜監督が意識したであろうテーマ性
三谷幸喜監督はこれまでも『ザ・マジックアワー』や『記憶にございません!』などで、虚構と現実のあいだに揺れる人間の滑稽さを描いてきました。
『スオミの話をしよう』でも同様に、“他人に語られる自分”というテーマを通じて、他者の視点でしか存在できないアイデンティティの不安定さを表現しています。
これはまさに、古典映画へのオマージュと三谷作品の本質が融合した演出だといえるでしょう。
『スオミの話をしよう』元ネタまとめ
- 映画は完全オリジナル脚本だが、古典映画へのオマージュが随所に見られる
- 英題「All About Suomi」は『イヴの総て』の構造を意識したもの
- 『サンセット大通り』などの要素を反転させた演出が特徴的
- タイトルの「スオミ」は再生と静謐を象徴する名前
- 三谷幸喜監督の作家性が詰まった、上質な群像劇として完成している