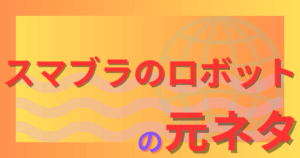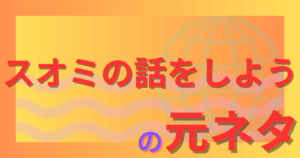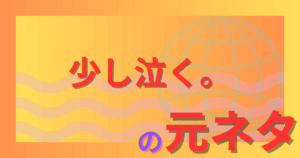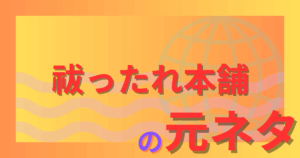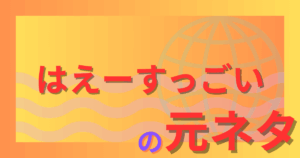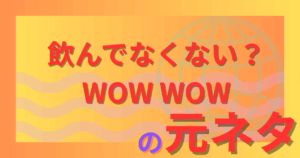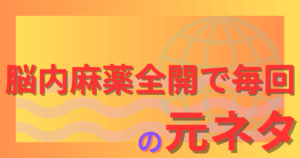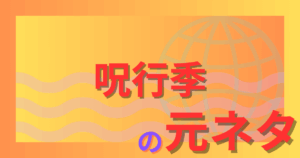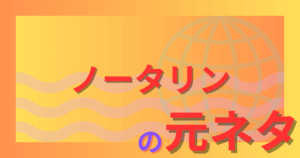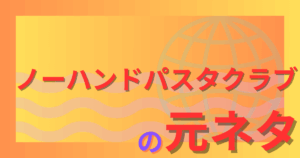任天堂の人気ゲーム『大乱闘スマッシュブラザーズ』シリーズに登場するキャラクター「ロボット」。
見た目は無機質なメカですが、その存在には任天堂の歴史を語るうえで欠かせない元ネタが隠されています。
実はこのロボット、1980年代のファミコン時代に登場した“ある周辺機器”がモデルとなっているのです。
この記事では、スマブラのロボットの元ネタとなったファミコンロボットの正体や仕組み、そしてスマブラでの再現ポイントを詳しく解説していきます。
スマブラのロボットの元ネタとは?
- ファミコンロボットとは何か
- どんな仕組みで動いていたのか
- スマブラに登場した経緯
ファミコンロボットとは何か
スマブラのロボットの元ネタは、**1985年に任天堂が発売した「ファミリーコンピュータ ロボット(HVC-012)」**です。
海外では「R.O.B.(Robotic Operating Buddy)」という名前で販売されました。
このロボットは、ファミコン本体と連動する珍しい周辺機器で、当時としては非常に画期的な存在でした。
単なるおもちゃではなく、テレビ画面の点滅信号を読み取って動作する**“光通信式のロボット”**というのが特徴です。
当時の対応ソフトは『ジャイロセット(Gyromite)』と『ブロックセット(Stack-Up)』の2本。
プレイヤーの操作によってロボットが実際にブロックを持ち上げたり、回転させたりと、現実世界で動くゲーム体験を提供していました。
どんな仕組みで動いていたのか
ファミコンロボットは、画面の明滅パターンをセンサーで読み取り、その信号をもとに腕や体を物理的に動かす構造でした。
たとえば、ゲーム内で特定のコマンドを入力すると、テレビ画面が点滅し、その信号を受けたロボットが「ブロックをつかむ」「離す」といった動作を実行します。
現代の視点で見ると原始的に思えますが、当時としては「家庭用ゲームとロボットの融合」という夢のあるコンセプトでした。
ファミコンブームの中でも非常に異色な存在で、任天堂が技術と遊びの融合に挑戦していた象徴的な製品といえます。
スマブラに登場した経緯
このファミコンロボットは長らく任天堂の歴史の中で“懐かしの周辺機器”として眠っていましたが、
『大乱闘スマッシュブラザーズX』(Wii版)でついにプレイアブルキャラとして復活しました。
スマブラでは「ロボット(R.O.B.)」という名前で登場し、原作で使用されていた**“ジャイロ”や“ビーム”といった要素**を技として再現。
たとえば、「ジャイロショット」は『ジャイロセット』で使われていた回転コマをモチーフにしており、元ネタを知る人ほどニヤリとする演出が多く含まれています。
また、スマブラ内の説明文では「古代遺跡で発掘された謎のロボット」として描かれており、過去と現在をつなぐ任天堂の象徴的キャラクターとして人気を集めています。
スマブラのロボットに込められた意味とは?
- 任天堂の歴史を象徴する存在
- “機械と人間の共存”というテーマ
- 懐かしさと未来をつなぐキャラクター
任天堂の歴史を象徴する存在
スマブラのロボットは、単なるファイターではなく、任天堂の挑戦と進化を象徴するキャラクターです。
ファミコンロボットが登場した1980年代、任天堂は「家庭用ゲームに新しい体験を取り入れる」ことに全力を注いでいました。
その精神が、スマブラシリーズにも受け継がれています。
“古いけれど新しい”存在としてロボットが参戦したことは、任天堂の歴史をリスペクトする姿勢の表れでもあります。
“機械と人間の共存”というテーマ
スマブラの中でロボットは、感情を持たないようでいて、どこか人間味を感じさせるキャラクターです。
これは、かつてファミコンロボットが「プレイヤーと協力する存在」として作られた背景を意識した演出といえるでしょう。
つまり、スマブラのロボットには「機械と人間が共に遊ぶ未来的な理想」が込められているのです。
懐かしさと未来をつなぐキャラクター
スマブラのロボットは、レトロゲーマーにとっては懐かしく、若い世代にとっては新鮮な存在。
その両者をつなぐ役割を果たしています。
過去の遺産を未来のプレイヤーへと伝える“架け橋”のようなキャラなのです。
スマブラのロボットの元ネタまとめ
- スマブラのロボットの元ネタは、1985年発売の**「ファミコンロボット(R.O.B.)」**
- 対応ソフトは『ジャイロセット』と『ブロックセット』の2本
- 画面の点滅信号を受け取って動くという光通信型の周辺機器
- スマブラでは“ジャイロショット”など元ネタを再現した技が登場
- 任天堂の歴史と挑戦を象徴するキャラクターとして今も愛されている