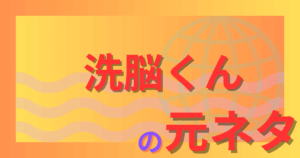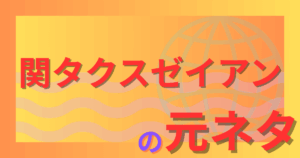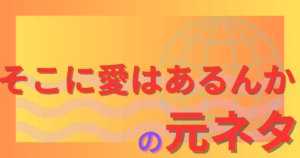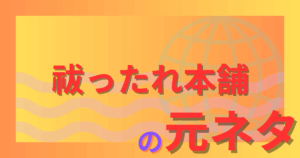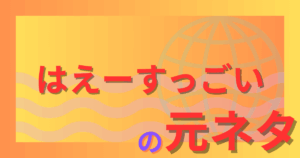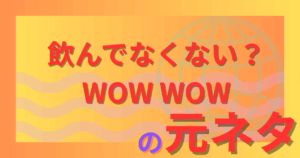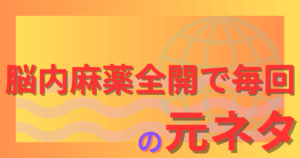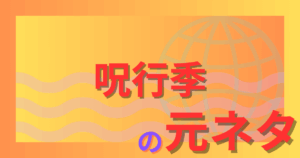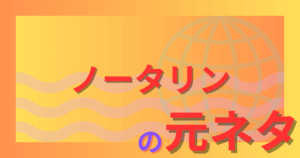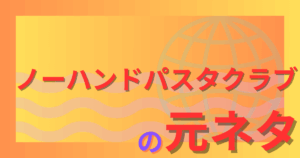『闇金ウシジマくん』の中でも特に衝撃的といわれるのが、「洗脳くん」編です。
このエピソードでは、人の心を支配する恐怖や、普通の人間が壊れていく様子がリアルに描かれています。
一部の読者の間では、「この話は実際の事件が元になっているのでは?」と話題になっています。
そのモデルとされているのが、北九州監禁殺人事件です。
この記事では、「洗脳くん」の元ネタや事件との共通点、作品に込められたメッセージについて詳しく解説します。
洗脳くんの元ネタとは?実際の事件との関係
- 洗脳くん編のあらすじと登場人物
- 北九州監禁殺人事件との共通点
- 洗脳手法や支配構造のリアリティ
洗脳くん編のあらすじと登場人物
「洗脳くん」編は、闇金業者・ウシジマのもとに現れる**“神堂(しんどう)”**という男を中心に展開します。
神堂は「洗脳屋」と呼ばれる人物で、人の心を巧みに操り、他人の金や人生を奪う危険な存在です。
彼は優しい言葉と恐怖を使い分けながら、ターゲットを徐々に支配していきます。
最初は“助けてくれる人”のように見えますが、次第に命令に逆らえなくなり、周囲の人間関係までも壊されてしまいます。
神堂の恐ろしさは、「暴力ではなく心理」で人を壊す点にあります。
この描写があまりにもリアルで、実際の洗脳事件を思い出す読者が多いのです。
北九州監禁殺人事件との共通点
「洗脳くん」編の元ネタとされているのが、2002年に発覚した北九州監禁殺人事件です。
この事件では、犯人が複数人の被害者を心理的に支配し、家族同士を争わせるよう仕向けるなど、極めて残酷な手口が使われました。
犯人は暴力だけでなく、「お前は悪い」「罰を与える」といった言葉を繰り返すことで、被害者を自ら支配下に置きました。
その結果、被害者たちは加害行為を“自分の意思”と錯覚し、互いを攻撃するようになります。
この「被害者同士を争わせる」「支配と服従の構造」という点が、『洗脳くん』と酷似しています。
また、性的な支配や極限状態での恐怖支配といった要素も、作品内に反映されています。
洗脳手法や支配構造のリアリティ
神堂が行う洗脳の過程は、現実の心理支配とほぼ同じ構造を持っています。
・相手の弱点を見抜く
・孤立させる
・褒めて安心させた後に恐怖を与える
・他人を敵視させ、逃げ道をなくす
こうした手順を繰り返すことで、ターゲットは自分で考える力を失っていきます。
つまり、「神堂に従うこと」だけが生き延びる道だと錯覚するのです。
このリアリティが、読者に「自分も洗脳されるかもしれない」という恐怖を与えました。
『洗脳くん』は単なるフィクションではなく、人間心理の“脆さ”を突きつける作品なのです。
洗脳くんが与えた衝撃と真鍋昌平の意図
- 作品で描かれた人間の弱さ
- 社会へのメッセージ性
- 視聴者・読者の受け止め方
作品で描かれた人間の弱さ
神堂に支配される登場人物たちは、決して特別な人間ではありません。
普通の会社員や主婦が、少しずつ心を蝕まれ、最終的には常識を失っていきます。
この描写によって、作者の真鍋昌平さんは「誰でも状況次第で洗脳されうる」という現実を示しています。
「意思が強ければ大丈夫」とは言い切れないのが、人間の怖さなのです。
社会へのメッセージ性
「洗脳くん」編は、単なるホラーやサスペンスではありません。
真鍋さんは、金と支配の構造が人間をどう変えるのかを描くことで、社会そのものへの問題提起をしています。
他人に依存し、考えることをやめると、誰でも簡単に利用されてしまう――。
その警鐘が作品全体を通して強く伝わってきます。
視聴者・読者の受け止め方
「洗脳くん」は、ウシジマくんシリーズの中でも**“最恐エピソード”**と評されています。
一度読むと忘れられないほど重く、現実に起きた事件を想起させるほどのリアリティがあるためです。
多くの読者が、「怖いけれど目が離せない」「現実の事件のようだった」と感じており、
シリーズの中でも最も深い心理描写が光る回として語り継がれています。
洗脳くんの元ネタまとめ
- 元ネタは北九州監禁殺人事件がモデルとされる
- 神堂の洗脳手法は実際の心理支配と酷似している
- 真鍋昌平氏は「誰でも壊れる」という人間の脆さを描いた
- 「洗脳くん」はウシジマくん史上もっとも恐ろしく、現実的なエピソード
この「洗脳くん」編は、単なる漫画の一話ではなく、人間の心の危うさを突きつける社会的な作品として今も語り継がれています。
読む際は、単なる恐怖ではなく、そこに込められたメッセージを感じ取ってみてください。