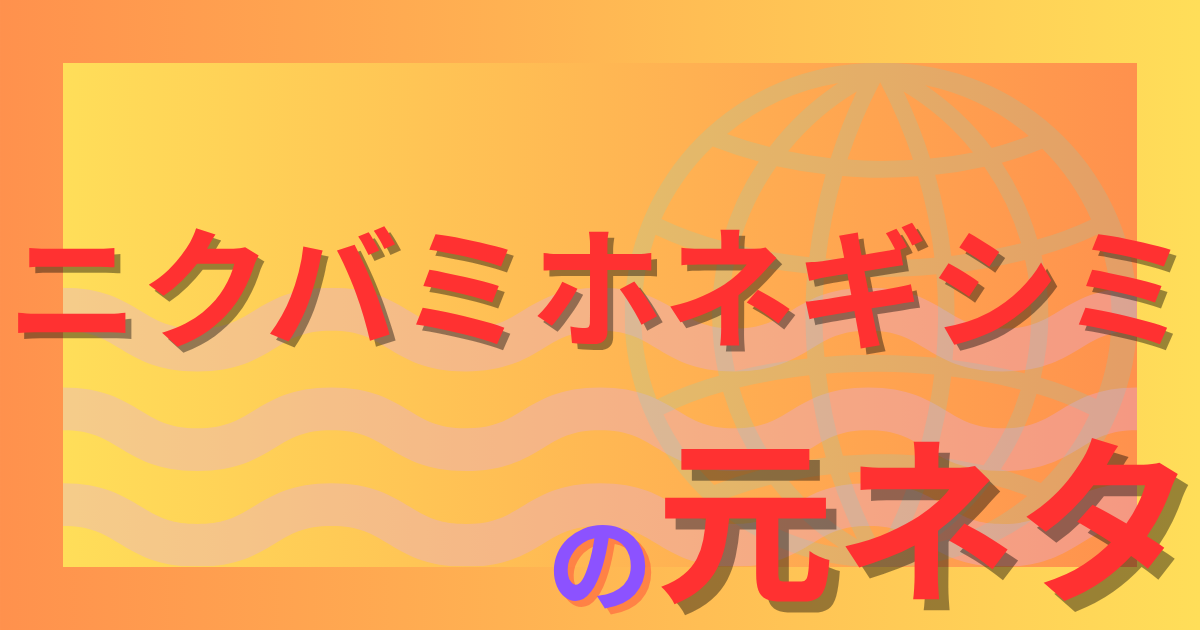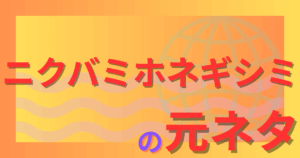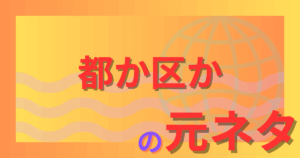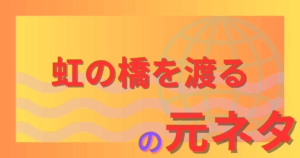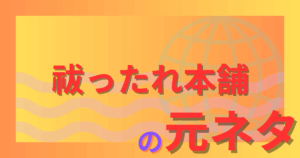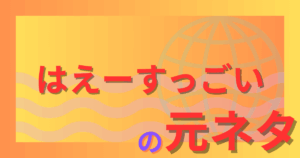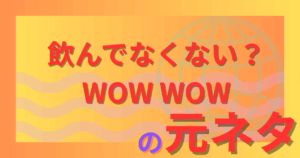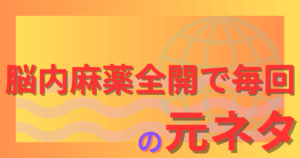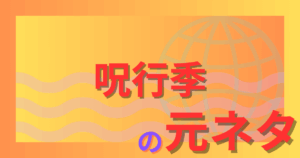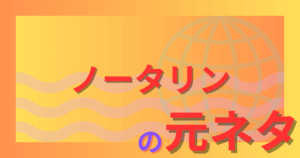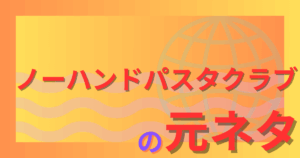現代ホラー漫画の中でも異彩を放つのが、パレゴリック氏の『ニクバミホネギシミ』です。
その不可解なタイトルと、読者を引き込む不気味な構成は「一体何が元ネタなのか?」と多くの人が気になっているポイントでもあります。
この記事では、『ニクバミホネギシミ』の元ネタや各話に隠された怪談・伝承のモチーフを、わかりやすく徹底解説します。
ニクバミホネギシミの元ネタとは?
- ニクバミホネギシミの意味と作品概要
- 元ネタはどこから来たのか
- モチーフとなった要素(都市伝説・民俗・クトゥルフ神話)
ニクバミホネギシミの意味と作品概要
漫画『ニクバミホネギシミ』は、パレゴリック氏によるホラー作品で、1999年と2023年という二つの時代を舞台にしています。
オカルト誌の編集者・犬吠埼しおいと、その甥が奇妙な儀式や怪異の謎を追う物語で、人間の恐怖と信仰の境界を描いた深い作品です。
タイトルの「ニクバミホネギシミ」は作中に登場する儀式の言葉であり、「肉を喰み、骨軋み」=命と死を繋ぐ呪文のような意味を持ちます。
現実と異界のあいだを揺らぐような、不気味な響きを意図的に作り出しているのが特徴です。
元ネタはどこから来たのか
この言葉は特定の伝承や実在の言葉に由来するものではなく、作者による完全な造語です。
ただし、作品全体には「知ってはいけない」「語ると現れる」といったネット怪談(洒落怖)系の構造が見られます。
また、儀式や怪異の描写には民俗信仰やクトゥルフ神話的要素が含まれており、複数の文化的恐怖を融合した作品といえます。
モチーフとなった要素(都市伝説・民俗・クトゥルフ神話)
- 「禁后」「牛の首」など、“知ると呪われる怪談”
- 道祖神や祠を題材にした日本の民俗信仰
- クトゥルフ神話に見られる宇宙的恐怖と儀式構造
これらの要素を組み合わせることで、**「語ること=儀式」**という独特の構成が生まれています。
各話に隠された怪談や伝承の元ネタ一覧
- 第1話〜第3話の元ネタ
- 第4話〜第6話の元ネタ
- 第8話・第11話・第12話の元ネタ
- 共通して描かれる儀式と禁忌の構造
第1話〜第3話の元ネタ
第1話「逅わせ鏡の紫」
この回は、「禁后(きんごう)」や「鏡の怪談」など、“見ると呪われる”タイプの伝承が元ネタと考えられます。
古い三面鏡を通して異界が映るという構図は、昔から語られる「鏡の向こうの世界」を連想させます。
作中では、“知ってはいけない読み方”を口にすることで怪異が発生するという、恐怖の連鎖が描かれます。
第2話「潭多観音(だんたかんのん)」
虫と仏像を題材にした土着信仰型の怪異がモチーフ。
観音像に巣くう虫が人間を侵食する描写は、信仰と穢れの表裏関係を象徴しています。
特定の怪談を直接元にしてはいませんが、「虫送り」「虫封じ」などの地方風習の再構築とみられます。
第3話「凶蛻の祖環(まがたのそわ)」
古代遺跡や出土物の祟りを扱う発掘系怪談が元ネタ。
発掘された“何か”が封印されていたものだと判明し、関わった人々に不幸が起きるという展開です。
禁足地や祟り神の民話構造をベースに、クトゥルフ的な「古代神」への言及も見られます。
第4話〜第6話の元ネタ
第4話「怪喰らい神歪み(けぐらいかんひずみ)」
道祖神の首を入れ替えるという民俗儀礼がテーマ。
村に伝わる神像を誤って壊し、別の像の首を付けたことから怪異が起こるという構成です。
信仰の形が歪む=神そのものが歪むという発想がホラーとして秀逸です。
第5話「辻の首人形」
首のない人形と犬神憑きの家系が登場します。
これは「犬神筋」や「祟り家系」の伝承を再構築したもので、血筋に宿る呪いがテーマ。
首という“命の象徴”を欠くことで、人間と神獣の境界が崩れる恐怖を描いています。
第6話「虚の椀に戻り雛」
海辺の村を舞台に、流し雛の風習を反転させた物語です。
災厄を流すために雛を川に流す行為が、逆に“災いを呼び戻す”展開になっています。
縞模様の椀を開ける禁忌は、神への冒涜=異界への扉を開く行為として描かれています。
第8話・第11話・第12話の元ネタ
第8話「幣呼払い」
有名な怪談「牛の首」と妖怪「件(くだん)」が元ネタとされています。
「牛の首」は“聞いた者は死ぬ話”、“件”は“未来を予言する怪異”として知られています。
これらを組み合わせ、「未来を知ることで破滅する」という知の呪いを描いています。
また、時間を越えて追う存在の描写には、ティンダロスの猟犬(クトゥルフ神話)も連想されます。
第11話「月光の岼籠(ぼうろう)」
月明かりの下に現れる異形の巨人が登場。
煙のような頭部、水かきのある手足などの特徴から、クトゥルフ神話のイサクアやダゴンの影響が見られます。
人間の理性では理解できない、**宇宙的恐怖(コズミックホラー)**を象徴する一編です。
第12話「産坊主の枯井戸」
井戸を中心に展開する回で、産女(うぶめ)伝承や井戸の怪異がモチーフ。
さらにクトゥルフ神話の「アボス」「ウッボ=サスラ」のような、生命を産む怪物神の要素も融合しています。
血と涎が混ざる井戸から新たな存在が生まれる描写は、生と死の境界を超える儀式として非常に印象的です。
共通して描かれる儀式と禁忌の構造
全話を通じて共通しているのは、**「知ること=儀式」「語ること=発現」**という構造です。
怪異を取材する行為そのものが儀式の一部になり、現実と物語の境界が曖昧になる。
読者自身もまた、「語り継ぐ」ことで儀式に参加してしまう――この構造こそ、『ニクバミホネギシミ』最大の恐怖です。
ニクバミホネギシミの元ネタまとめ
- 元ネタは明確な一つではなく、都市伝説・民俗信仰・クトゥルフ神話の融合
- 各話には鏡・虫・首・井戸などの日本的怪談モチーフが多数登場
- 物語全体は「知ること=儀式」というメタ的な恐怖構造で貫かれている