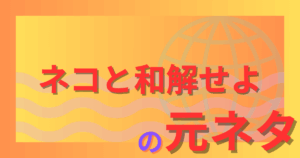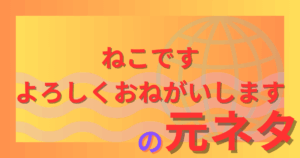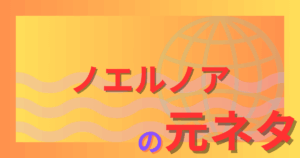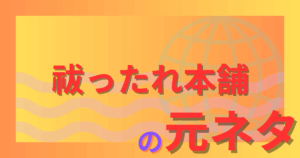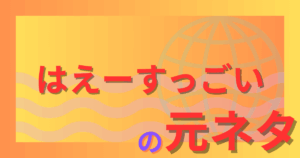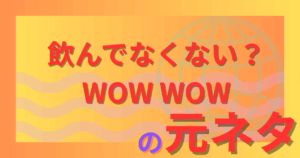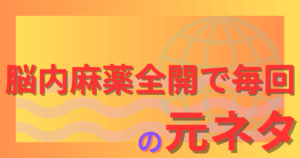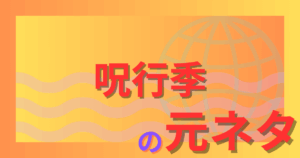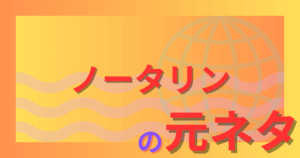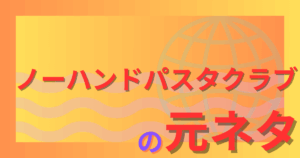街中やSNSで見かける「ネコと和解せよ」という言葉。かわいらしい響きながらも、どこか神秘的で意味深なフレーズですよね。実はこの言葉には、意外な宗教的背景と、ネット文化の融合による偶然の産物という一面があります。
この記事では、「ネコと和解せよ」の元ネタや由来、そしてどのようにしてネットミームとして広まったのかをわかりやすく解説します。
ネコと和解せよの元ネタとは?流行のきっかけ
- 「神と和解せよ」の看板が元ネタ
- なぜ「神」が「ネコ」に変化したのか
- ネットミームとしての広がり
「神と和解せよ」の看板が元ネタ
「ネコと和解せよ」の元ネタは、東北地方を中心に見られる宗教団体・聖書配布協力会などが設置した**「神と和解せよ」**という看板です。
黒い背景に白や黄色の文字で「神と和解せよ」と書かれた看板は、キリスト教の教えの一節を引用したもので、「神との和解を通じて救われる」という意味を込めて設置されたものでした。
長年、道路沿いや住宅地に立てられていたこの看板が、ある日「神」が「ネコ」に見えるように変わったことが、ミーム誕生のきっかけとなりました。
なぜ「神」が「ネコ」に変化したのか
「神と和解せよ」という文字のうち、「神」の部分が風化や塗装の剥がれ、あるいは落書きなどによって「ネコ」と読めるようになった事例が報告されています。
つまり、もともとは宗教的な看板の劣化や偶然によって、「ネコと和解せよ」という新しいフレーズが生まれたのです。
この予想外の変化がネット上で注目され、「なんて平和的なメッセージなんだ」「確かにネコとは和解したい」と話題になり、Twitter(現X)や掲示板を通じて拡散しました。
ネットミームとしての広がり
「ネコと和解せよ」はその後、猫好きやネットユーザーの間で平和と癒しの象徴的フレーズとして親しまれるようになります。
Tシャツ、ステッカー、キーホルダーなどのグッズ化も進み、「ネコと和解せよ」は単なる看板のパロディを超えた文化的アイコンに成長しました。
ネットでは、「怒っている猫の画像と組み合わせて投稿」したり、「ネコとの仲直りを促す言葉」として使われたりと、多様な文脈でユーモラスに使われ続けています。
ネコと和解せよ まとめ
- 元ネタは宗教看板「神と和解せよ」
- 風化や改変によって「ネコ」と読めるようになったことから誕生
- SNSで拡散し、猫好きとネット文化の融合としてミーム化
- グッズ化などを通じて定着し、今では平和的メッセージとして親しまれている