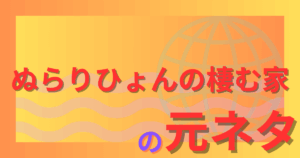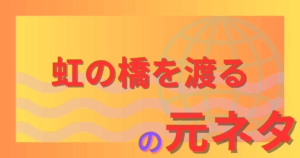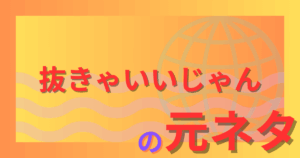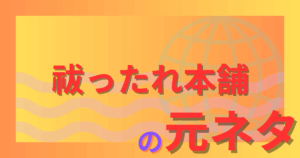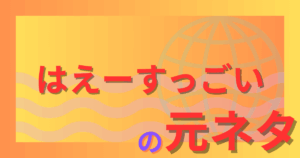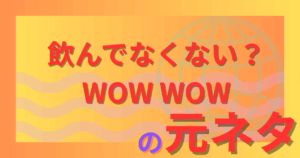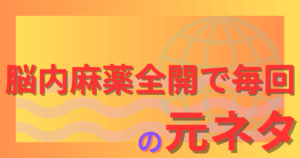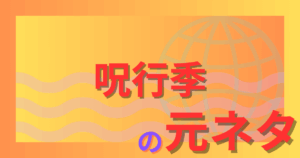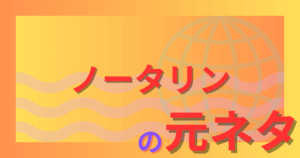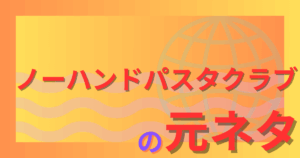漫画『ぬらりひょんの棲む家』は、**「実家に知らない男が住みついている」**という異常な設定から始まるホラー作品です。
読者の間では「妖怪のぬらりひょんが元ネタなのでは?」「実話をモチーフにしているのでは?」といった考察が飛び交い、今やSNSを中心に大きな話題を呼んでいます。
この記事では、『ぬらりひょんの棲む家』の元ネタやタイトルに込められた意味、そして“人間の狂気”に焦点を当てた恐怖の本質をわかりやすく解説します。
ぬらりひょんの棲む家の元ネタとは?流行のきっかけを解説
- ぬらりひょんという妖怪の伝承がモチーフ
- 実家に侵入者が“居つく”という構図
- SNSでの「胸くそ展開」が話題に
ぬらりひょんという妖怪の伝承がモチーフ
ぬらりひょんは、日本の妖怪伝承の中でも特に不気味で象徴的な存在です。
どこからともなく人の家に現れ、まるで自分の家のように振る舞うという奇妙な妖怪として知られています。
『ぬらりひょんの棲む家』というタイトルは、この伝承をベースにしたもの。
「他人の家に勝手に上がり込む」「家族に溶け込んで支配する」という構図は、まさに現代版ぬらりひょんといえるでしょう。
作中では、主人公の実家に見知らぬ中年男性・沼尻が住みつき、家族までもが彼を受け入れてしまいます。
その不条理な状況が、妖怪のように“侵入し支配する存在”としてのぬらりひょん像を現代的に再現しているのです。
実家に侵入者が“居つく”という構図
本作の恐怖の根幹は、「家」という最も安全な場所が奪われることにあります。
自分の家に帰ったのに、そこはすでに他人の支配下――。
その異様な空気が、読者にじわじわとした不安と恐怖を与えます。
ぬらりひょんの「居つく」という行動をモチーフにしながら、“日常の侵略”をテーマにした心理ホラーとして成立しているのが、この作品の最大の特徴です。
SNSでの「胸くそ展開」が話題に
『ぬらりひょんの棲む家』は、妖怪モチーフに加えて、人間の狂気と支配欲を描いた物語として注目を集めました。
「読後感が最悪」「胸くそ悪いけど目が離せない」などの感想がSNSで広まり、口コミで急速に話題に。
“ぬらりひょん”というキャッチーなタイトルと、“現実味のある恐怖”が融合した結果、多くの読者の印象に残る作品となりました。
ぬらりひょんの棲む家の元ネタに込められた意図と恐怖の本質
- 「家に棲みつく」=安心の崩壊という演出
- 妖怪モチーフを現代的ホラーに昇華
- 元ネタよりも“人間のぬらりひょん性”が恐怖
「家に棲みつく」=安心の崩壊という演出
タイトルの「棲む家」という言葉には、**“他者に支配された空間”**という不穏な響きがあります。
家は本来、家族が安心して過ごす場所。しかしそこに“異物”が入り込むことで、
安心が崩壊し、日常が異常に変わる――それが本作の核心です。
つまり、「棲む家」という表現は、ぬらりひょん=侵入者=崩壊の象徴として機能しているのです。
妖怪モチーフを現代的ホラーに昇華
本作には実際の妖怪は登場しません。
それでも、ぬらりひょんの「侵入」「支配」という象徴を通して、人間の恐ろしさが浮かび上がります。
つまり、作者が描いたのは“怪異”ではなく、“人間の内に潜む怪異”。
「他人の人生に入り込み、気づかぬうちに支配していく」――
このぬらりひょん的な人間像こそが、現代社会の闇を映す鏡なのです。
元ネタよりも“人間のぬらりひょん性”が恐怖
読者が感じる最大の恐怖は、「ぬらりひょん」が実在の妖怪ではなく人間そのものである点です。
見知らぬ他人が家庭に入り込み、やがて居場所を奪っていく。
その姿は、まるで社会や人間関係の中で起きる“侵食”の比喩のようでもあります。
ぬらりひょん=心に潜む支配欲。
この作品は、そんな人間の内側に潜む“見えない恐怖”を描いた心理ホラーなのです。
ぬらりひょんの棲む家の元ネタまとめ
- 元ネタは妖怪「ぬらりひょん」の伝承に由来しているが、内容は人間の支配と狂気を描いた現代ホラー。
- 家という“安心の象徴”が侵食されていく過程が、最大の恐怖演出となっている。
- 妖怪よりも怖いのは人間――それが『ぬらりひょんの棲む家』の真のテーマである。