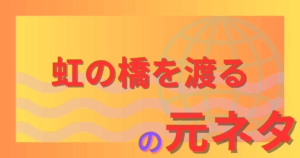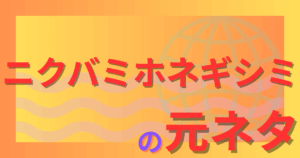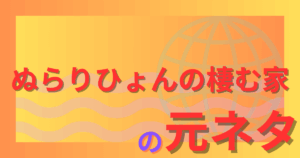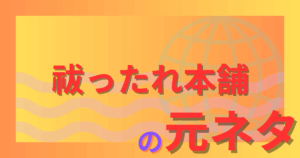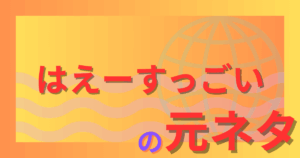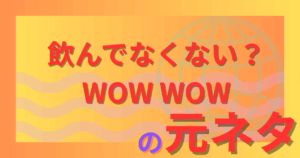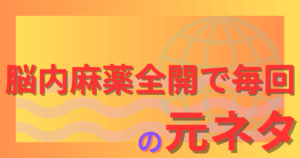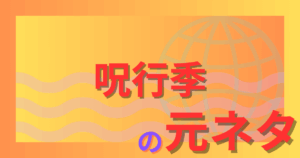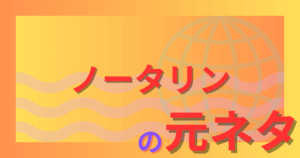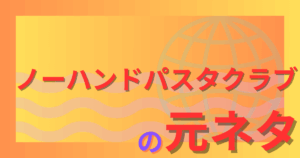「虹の橋を渡る」という言葉は、ペットとの別れを表すときによく耳にする表現です。
亡くなったペットが虹の橋のたもとで待っていて、いつか飼い主と再会する——。そんな温かくも切ないイメージが、多くの人の心を癒やしてきました。
この記事では、「虹の橋を渡る」という表現の元ネタとなった詩の起源や意味をわかりやすく解説します。
虹の橋を渡るの元ネタとは?
- 虹の橋の詩の起源はどこから?
- 詩の作者は誰?実在の人物だった?
虹の橋の詩の起源はどこから?
「虹の橋」は、もともと英語で「Rainbow Bridge」と呼ばれる詩が元になっています。
この詩は、亡くなったペットが天国に行く前にたどり着く“虹の橋のふもと”で、元気を取り戻しながら飼い主を待つという物語です。
やがて飼い主が亡くなり、その場所に来ると、ペットが駆け寄って再会を喜び、一緒に虹の橋を渡って天国へ行く——という感動的な内容になっています。
この詩は欧米で広く知られ、インターネットや書籍を通して世界中に広まりました。
その優しい世界観が共感を呼び、「虹の橋を渡る=ペットが亡くなる」という表現として定着していったのです。
詩の作者は誰?実在の人物だった?
この詩には長い間「作者不詳」という時期がありました。
しかし近年になって、スコットランドの女性が1950年代に亡くした愛犬を想って書いた詩が原点だったとされています。
彼女は芸術家であり、自分の気持ちを詩として残したことがきっかけで、後にその内容が口コミや手紙などで世界中に広がりました。
もともとは個人的な悲しみを表現した詩でしたが、次第に「ペットを失った人たちの心を癒やす詩」として共有されるようになり、やがて“虹の橋”という言葉そのものが「別れと再会の象徴」になったのです。
虹の橋の詩が広まった理由と意味
- どんな内容の詩なのか
- 日本で「虹の橋を渡る」が定着した理由
- 「虹の橋」の象徴するものとは
どんな内容の詩なのか
詩の中では、亡くなったペットたちは天国の手前にある美しい草原で暮らしています。
そこでは、病気もなく、傷もなく、若く元気な姿に戻り、仲間たちと走り回ることができます。
ただひとつ足りないのは、飼い主がいないこと。
やがて飼い主が亡くなってその場所に現れると、ペットはすぐに気づいて駆け寄り、再会の喜びを分かち合いながら、一緒に虹の橋を渡っていくのです。
この物語は、ペットを家族の一員と考える人々の心に深く響き、「虹の橋」という比喩が悲しみをやさしく包み込む象徴となりました。
日本で「虹の橋を渡る」が定着した理由
日本でこの言葉が広まったのは、ペットを“家族”と考える文化が定着したことが大きな理由です。
動物病院やペット霊園などで「虹の橋」の詩が紹介されるようになり、追悼文やSNSの投稿などでも自然と使われるようになりました。
今では、ペットロスに悩む人を励ます優しい言葉として広く受け入れられています。
「虹の橋」の象徴するものとは
「虹の橋」は、単に天国への道ではなく、“再会の約束”や“永遠のつながり”を意味する象徴です。
この考え方は、北欧神話に登場する神々と人間をつなぐ「ビフレストの虹の橋」などとも重なり、古くから人々の心に存在してきた“虹=世界をつなぐ道”というイメージを引き継いでいます。
だからこそ、「虹の橋を渡った」と聞くと、悲しみの中にも「また会える」という希望を感じられるのです。
虹の橋を渡るの元ネタまとめ
- 「虹の橋を渡る」は、英語詩「Rainbow Bridge」が元ネタ
- 1950年代にスコットランドの女性が愛犬を想って書いた詩が原点
- ペットが天国の手前で飼い主を待ち、再会して共に虹を渡る物語
- 日本ではペットロスを癒やす言葉として広く定着
- 虹は「再会」「永遠の絆」を象徴する希望のモチーフ