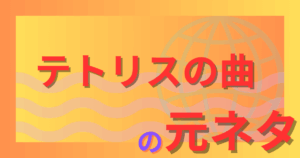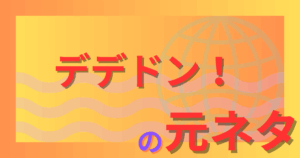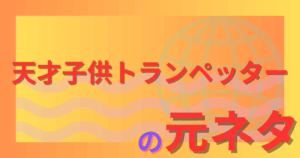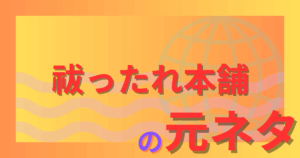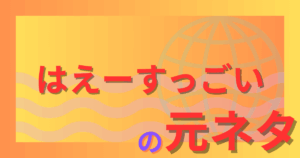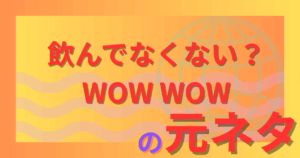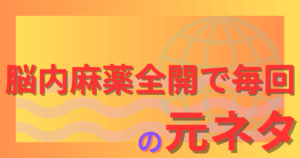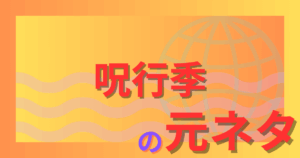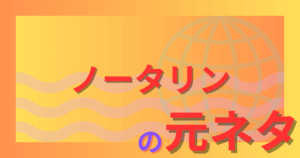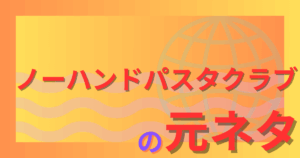世界的に知られるパズルゲーム「テトリス」。その中でも特に印象的なのが、プレイ中に流れるあの軽快なBGMです。耳に残るメロディは誰もが一度は聞いたことがあるでしょう。実はこの曲には、ロシア民謡を原曲とする意外なルーツがあるのです。
この記事では、テトリスの曲の元ネタやゲームボーイ版での採用背景、他のBGMの出典まで詳しく解説します。
テトリスの曲の元ネタとは?流行のきっかけ
- テトリスの曲の正体はロシア民謡「コロベイニキ」
- ゲームボーイ版で採用された背景
- 作曲者・田中宏和のアレンジについて
テトリスの曲の正体はロシア民謡「コロベイニキ」
テトリスで最も有名な「Type A」のBGMは、**19世紀のロシア民謡『コロベイニキ(Korobeiniki)』**が元ネタです。
この曲はもともと、行商人と少女の恋を描いた詩をもとに作られた民謡で、ロシアでは古くから親しまれていました。哀愁を帯びつつもリズミカルなメロディが特徴で、民族的な響きがテトリスの世界観にぴったり合致していたのです。
この旋律が1989年に発売されたゲームボーイ版テトリスで使用され、世界中で知られるようになりました。現在では「テトリスのテーマ」として、ゲーム音楽の象徴的存在となっています。
ゲームボーイ版で採用された背景
テトリスの原作は、ソビエト連邦の科学者アレクセイ・パジトノフ氏によって開発されました。当初のバージョンにはBGMが存在せず、静かなパズルゲームとして登場します。
その後、任天堂がゲームボーイ版を制作する際に、「ロシアらしさを演出したい」という意向から民謡を使用することになりました。
数ある候補の中から選ばれたのが、「コロベイニキ」だったのです。結果として、この選曲がテトリスを**“文化的にも象徴的なゲーム”へと押し上げる要因**となりました。
作曲者・田中宏和のアレンジについて
任天堂の作曲家である田中宏和氏は、「コロベイニキ」の旋律を8ビット音源で大胆に再構成しました。
テンポを速め、リズムを強調することで、プレイヤーの集中力と緊張感を高めるよう設計されています。
このアレンジは後にさまざまなリミックスやゲーム版に受け継がれ、**“テトリスの定番サウンド”**として定着しました。
テトリスの他のBGMとその元ネタ
- Type Bはオリジナル曲
- Type Cはバッハの「メヌエット」が原曲
- その他のテトリス作品に使われたクラシック曲
Type Bはオリジナル曲
「Type B」は田中宏和氏による完全オリジナル曲です。
コロベイニキとは異なり、どこかメカニカルで緊迫感のあるリズムが特徴。ステージクリア時の達成感と緊張感を両立させるよう設計されています。
クラシック曲の引用はなく、田中氏独自のゲームサウンド哲学が光る一曲です。
Type Cはバッハの「メヌエット」が原曲
「Type C」では、**J.S.バッハの『フランス組曲第3番 ロ短調 BWV814』の「メヌエット」**が引用されています。
優雅で落ち着いた旋律が特徴で、Type Aの激しいリズムとは対照的。集中しながらも心を落ち着かせたいプレイヤーに人気がありました。
このクラシカルな雰囲気が、テトリスに独特の深みを与えています。
その他のテトリス作品に使われたクラシック曲
一部のアーケード版や海外版テトリスでは、チャイコフスキーの『くるみ割り人形』の「ロシアの踊り(トレパーク)」など、別のクラシック曲が使用された例もあります。
さらに、現代ではボーカロイド曲「テトリス(重音テト)」などにも「コロベイニキ」のメロディが引用され、“テトリスの象徴”として音楽文化に定着しています。
テトリスの曲の元ネタまとめ
- テトリスの代表曲「Type A」はロシア民謡「コロベイニキ」が元ネタ
- 「Type C」はバッハの「メヌエット」が原曲
- 「Type B」は田中宏和氏によるオリジナル曲
- ゲームボーイ版の採用で世界的に広まった
- 現代でも多くのリミックスやカバーで使われ続けている