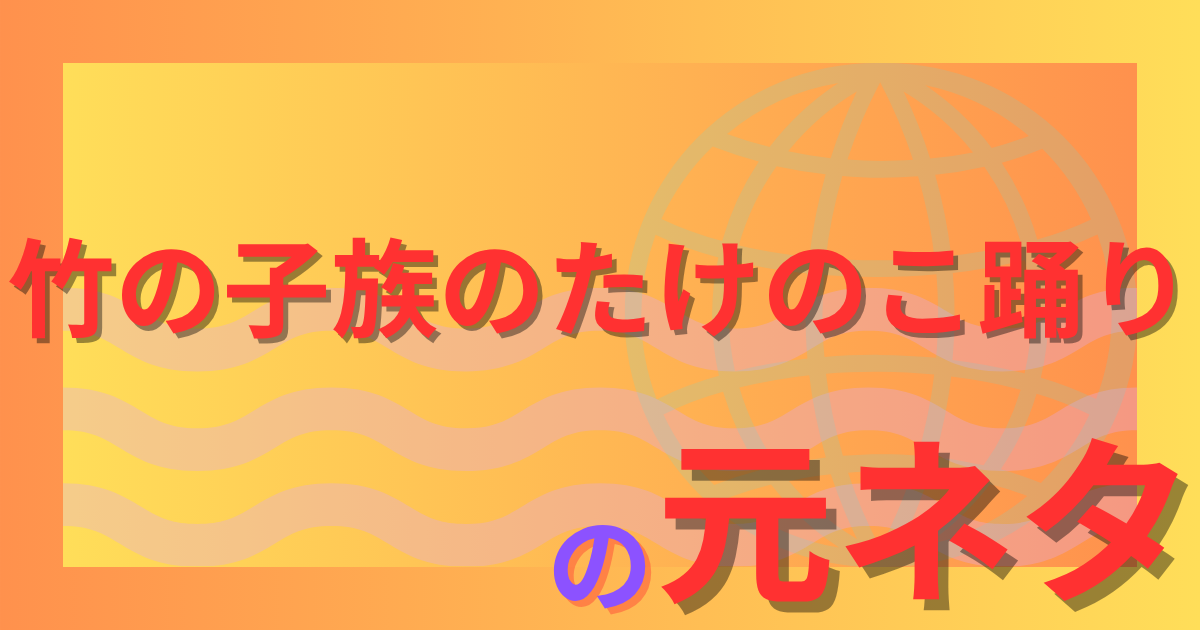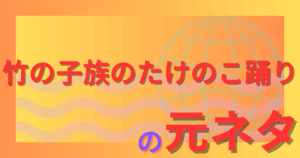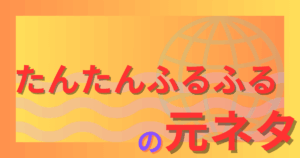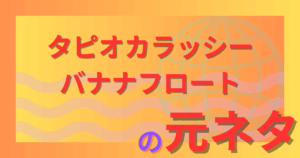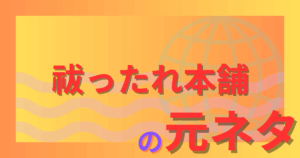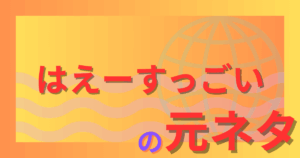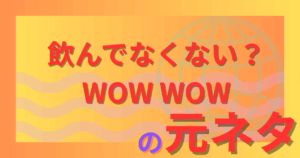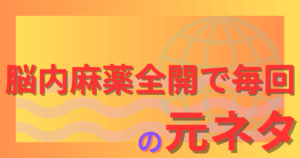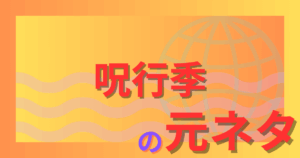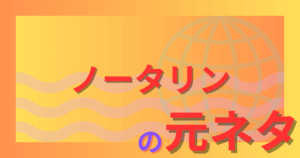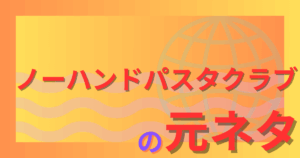1980年代に原宿で一世を風靡した「竹の子族(たけのこぞく)」。その中で踊られていたという「たけのこ踊り(タケノコダンス)」が、令和の時代に再び注目を集めています。
当時の映像や音楽をリミックスした動画がTikTokなどで拡散し、「この踊りの元ネタは?」「本当にあったの?」と話題になっているのです。
この記事では、竹の子族のたけのこ踊りの元ネタや音楽との関係、そして現代での再ブームの理由をわかりやすく解説します。
竹の子族のたけのこ踊りの元ネタとは?当時の文化と音楽背景を解説
- 竹の子族とは?原宿を中心に生まれた80年代カルチャー
- たけのこ踊りの元ネタはジンギスカン?音楽と振付の関係
- 本当に“たけのこ踊り”は存在したのか?映像と証言の真相
竹の子族とは?原宿を中心に生まれた80年代カルチャー
竹の子族とは、1980年代前半に原宿の歩行者天国などで、カラフルな衣装を着た若者たちがディスコ調の音楽に合わせて踊っていたグループの総称です。
派手なファッションやダンスが特徴で、当時の若者文化を象徴する存在でした。
竹の子族の名前は、原宿のブティック「竹の子」の常連客たちが中心だったことから生まれたものです。つまり、「たけのこ踊り」は、そんな彼らが自然発生的に踊っていたステップやリズムを指す言葉でした。
たけのこ踊りの元ネタはジンギスカン?音楽と振付の関係
「たけのこ踊り」の元ネタとして最も有力とされているのが、1979年に世界的にヒットしたドイツのディスコソング「ジンギスカン(Genghis Khan)」です。
当時の竹の子族がこの楽曲を流して踊っていた映像が複数残っており、軽快なリズムとユーモラスな動きが“たけのこ踊り”と呼ばれるようになったと考えられています。
ただし、明確な“公式の振付”が存在するわけではなく、当時の若者たちが自由に踊っていた動きを後世の人々が「たけのこ踊り」とまとめて呼んだ、という説が濃厚です。
本当に“たけのこ踊り”は存在したのか?映像と証言の真相
現在SNSで流行している「たけのこ踊り動画」は、実際の80年代映像を編集・リミックスしたものであることが多いです。
YouTubeなどには、当時のニュース映像やストリート映像を加工したものが多数投稿されており、**オリジナルの“振付”というよりは、過去の映像の再構成によって生まれた現代的な“たけのこ踊り”**といえます。
つまり、「竹の子族=たけのこ踊り」というより、「竹の子族の映像をもとにした現代リミックス=たけのこ踊り」という構図なのです。
たけのこ踊りはなぜ再び話題に?現代SNSでのリバイバル現象
- YouTubeやTikTokでの拡散経緯
- リミックス文化が再燃させたたけのこ踊りブーム
- 昭和カルチャー再評価の流れと今後の注目点
YouTubeやTikTokでの拡散経緯
2024年ごろから、「竹の子族の映像を編集した動画」や「ジンギスカンに合わせた振付動画」がTikTokで話題になりました。
特に「たけのこ踊り」というフレーズが使われた動画は、80年代の映像をリミックスしたコミカルな仕上がりで人気を博しています。
SNSのコメント欄では「本当に昔の人がこんな踊りしてたの?」「実際にあった文化なのがすごい」といった声も多く、若い世代にとっては“未知の昭和カルチャー”として新鮮に映っています。
リミックス文化が再燃させたたけのこ踊りブーム
現代のSNS文化では、「古い映像×新しい編集」の組み合わせでブームが生まれることが増えています。
たけのこ踊りもその代表で、当時のストリート映像にリズムを合わせて再編集した“リミックス動画”が流行の火付け役となりました。
**「懐かしいけど新しい」**という独特の感覚が、多くのユーザーの心をつかんだと言えるでしょう。
昭和カルチャー再評価の流れと今後の注目点
近年、昭和の音楽やファッションが再び注目を集めています。
レトロブームの中で、竹の子族のようなサブカルチャーも再評価され、「昭和の自由な若者文化」への憧れや好奇心がSNS世代に広がっているのです。
今後は、当時の映像や音楽を再現したイベント、昭和リバイバル系コンテンツの中で、たけのこ踊りが“象徴的な存在”として扱われる可能性もあります。
竹の子族のたけのこ踊りの元ネタまとめ
- 竹の子族は1980年代に原宿で流行したディスコ系ストリートカルチャー。
- たけのこ踊りの元ネタとされる楽曲は「ジンギスカン」。
- 振付は決まっておらず、当時の自由な踊りが映像を通じて「たけのこ踊り」と呼ばれるようになった。
- 現代ではリミックス動画を通じて再ブームを迎え、昭和カルチャー再評価の象徴となっている。