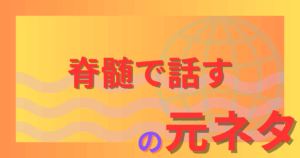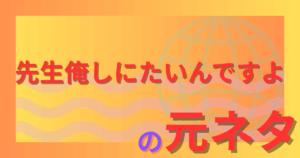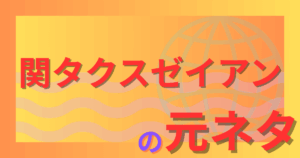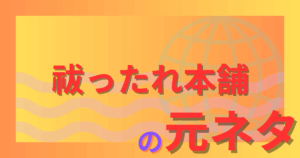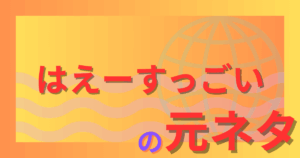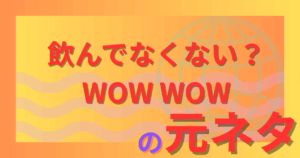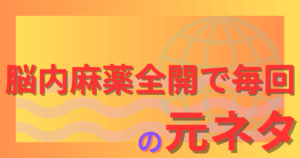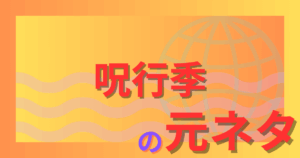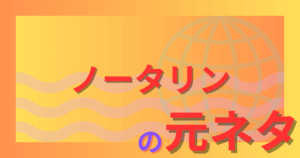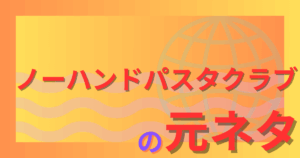思わず感情のままに話してしまうことを、ネットでは「脊髄で話す」と表現することがあります。
この言葉は、もともと「脊髄トーク」というネットスラングから生まれたものです。
この記事では、脊髄で話すの元ネタや脊髄トークの意味、そしてにじさんじでの使われ方についてわかりやすく解説します。
脊髄で話すの元ネタとは?
- 脊髄トークの由来と意味
- どこで使われ始めた言葉なのか
脊髄トークの由来と意味
「脊髄で話す」という表現の元になっているのが、ネットスラングの**「脊髄トーク」**です。
この言葉は、考えるより先に口が動いてしまうような発言を指し、
生理学の「脊髄反射(spinal reflex)」をもとに作られた比喩表現です。
脊髄反射とは、脳の判断を介さずに体が反応すること。
そのため「脊髄トーク」は、「思考を通さずに話している人」「感情で反応してしまう人」を
少し皮肉を込めて表す言葉として使われています。
どこで使われ始めた言葉なのか
「脊髄トーク」や「脊髄で話す」という言葉は、
2000年代後半〜2010年代前半の2ちゃんねる文化から生まれたと考えられています。
当時は「脊髄反射レス」や「脊髄反応」という形で、
相手の感情的な反応をからかうネットスラングとして広まりました。
その後、SNSや動画配信の普及によって、
「脊髄トーク」「脊髄でしゃべる」「脊髄で反応してて草」といった派生表現が登場。
今では考える前に反応する人を表すネット文化的な言葉として定着しています。
ネットスラング「脊髄トーク」の意味をわかりやすく解説
- ネットでの使われ方とニュアンス
- なぜ再び注目されているのか
- にじさんじでも話題になった「脊髄トーク」
- 脊髄で話すの元ネタと脊髄トークの意味まとめ
ネットでの使われ方とニュアンス
「脊髄トーク」は、冷静さより感情や勢いで発言する人をからかうときに使われます。
SNSや掲示板での例を挙げると、
- 「脊髄で話してて草」
- 「脊髄トークしてるな」
- 「思考が口に追いついてない」
といった形が多いです。
どれも「考える前に言ってしまってる」「反射的に反応している」という意味で、
ユーモアを込めて指摘する使われ方が一般的です。
なぜ再び注目されているのか
2000年代に生まれた言葉ですが、
近年はSNS文化の加速によって再び注目を集めています。
特にX(旧Twitter)では、思ったことを即座に投稿する流れが一般的で、
そうした「即反応型の会話文化」を象徴する言葉として「脊髄トーク」が再ブームになっています。
また、YouTubeや配信界隈でも、
瞬時の返しやリアクションを楽しむスタイルが人気で、
「脊髄でしゃべってる」などのコメントが冗談交じりに使われています。
このように、「脊髄トーク」は感情表現のスピード感を表す言葉として親しまれているのです。
にじさんじでも話題になった「脊髄トーク」
VTuberグループ「にじさんじ」の配信でも、
リスナーの間で「脊髄トーク」という言葉が話題になることがあります。
にじさんじのライバーたちは、リアクションが早く感情表現が豊かなトークスタイルが特徴で、
その瞬発的な発言が「脊髄でしゃべってる」と冗談まじりに言われることがあるのです。
特にコラボ配信や雑談配信では、
テンポの良い会話や思わず出た一言が面白さにつながることも多く、
ファンの間では「脊髄トーク」という言葉がにじさんじ的リアクションの象徴として定着しています。
脊髄で話すの元ネタと脊髄トークの意味まとめ
- 「脊髄で話す」はネットスラング「脊髄トーク」が元ネタ
- 意味は「考えるより先に話す」「感情で即反応する」
- 2ちゃんねる文化から生まれ、SNSで再び流行
- にじさんじのようなリアクションの速いトークにも通じる
- 皮肉とユーモアを込めたネット定番ワード