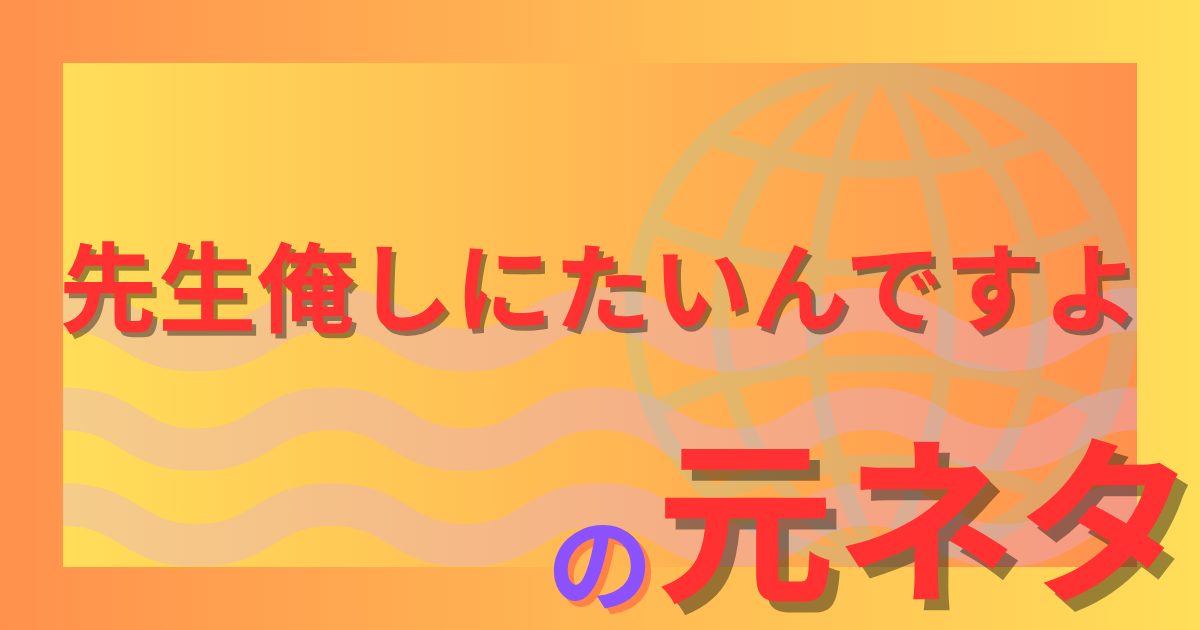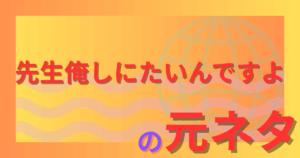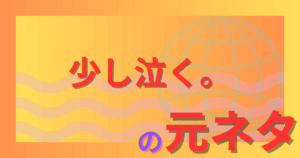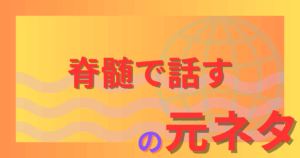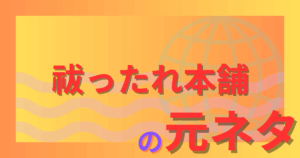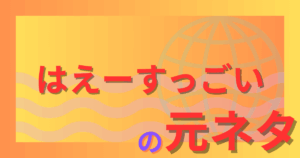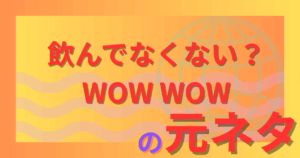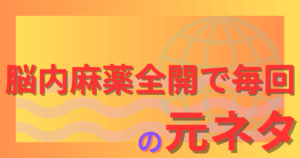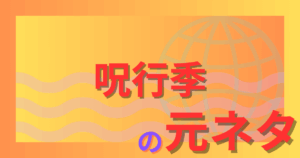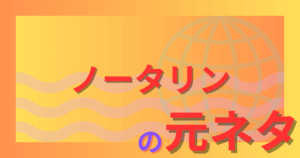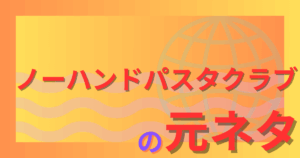「先生、俺しにたいんですよ」というフレーズを見かけて、思わず気になった人も多いのではないでしょうか。
どこか切実で、同時にネタのようにも感じるこの言葉。実はネットの中で特定の構文として広まり、さまざまな形で使われています。
この記事では、「先生俺しにたいんですよ」の元ネタや発祥の説、ネットで流行した理由についてわかりやすく解説します。
先生俺しにたいんですよの元ネタとは?
- 元ネタは漫画『ボーイズ・オン・ザ・ラン』という説
- 最初に投稿されたとされるX(旧Twitter)のポスト
- 「先生俺しにたいんですよ」構文とは?
元ネタは漫画『ボーイズ・オン・ザ・ラン』という説
このフレーズの**元ネタとしてよく名前が挙がるのが、漫画『ボーイズ・オン・ザ・ラン』**です。
一部の読者のあいだで、「登場人物が“先生”に悩みを打ち明ける場面がある」という説が語られており、そこからこの台詞が広まったという見方が生まれました。
ただし、実際にそのままのセリフが登場するという確証はなく、漫画が直接の出典というより“イメージ的なつながり”が語られている段階です。
そのため、「ボーイズ・オン・ザ・ラン」はあくまで参考説のひとつとして捉えるのが良いでしょう。
最初に投稿されたとされるX(旧Twitter)のポスト
現在のように「先生、俺しにたいんですよ」が話題になったのは、X(旧Twitter)での投稿がきっかけとされています。
日常的な内容や感情表現の中にこのフレーズを入れて“オチ”にするスタイルが話題となり、瞬く間に拡散しました。
つまり、特定の作品が出典というより、ネット文化の中で自然発生的に生まれた言葉と考えられます。
そのユニークなリズムと感情の強さが、多くのユーザーの共感と笑いを呼びました。
「先生俺しにたいんですよ」構文とは?
このフレーズは、今では一種の“構文ミーム”として認識されている表現です。
特徴は、感情の高まりを表現したあとに「先生、俺しにたいんですよ」という言葉で一気に空気が変わる点にあります。
多くの場合、前半では恋愛や悩みなど真剣な話をしているように見せかけて、最後にこの一言で締めくくるという形式が使われます。
この“感情の落差”が生む独特の間(ま)が面白さにつながり、ネタとして定着しました。
つまり、「先生俺しにたいんですよ」というのは単なる台詞ではなく、感情の落差や唐突さを笑いに変える文体的なフォーマットだといえます。
ネットで広まった理由と使われ方
- 性的な文脈から派生したネタツイ構文
- 「先生、俺○○したいんすよ」として派生・定着
- 現在の使われ方とミーム文化への影響
性的な文脈から派生したネタツイ構文
このフレーズが大きく拡散した背景には、性的な文脈で使われたネタツイートの影響もあります。
強い欲望や感情を真剣に語ったあとに「先生、俺しにたいんすよ」で締めるという形が、
“欲望と絶望の落差”による面白さを生み、話題になりました。
こうした使い方は次第に広まり、シリアスな雰囲気とネタ感を同時に出せる“独特の構文”として人気を集めました。
「先生、俺○○したいんすよ」として派生・定着
この構文はその後アレンジされ、
「先生、俺眠いんすよ」「先生、俺チョコ好きなんすよ」など、
「死にたい」の部分を入れ替えたバリエーションが登場しました。
重すぎる印象を和らげつつ、言葉のリズムだけを残すことで、
日常ネタやユーモアとして使いやすくなり、今では汎用的なネットスラングとして定着しています。
現在の使われ方とミーム文化への影響
現在では「先生、俺しにたいんですよ」は、ツイート文学やネットミームの一種として扱われています。
特定の作品や人物に由来するわけではなく、
“真剣さとおかしさが同居する構文”というスタイル自体がネタになっているのが特徴です。
この独特の言い回しは、感情表現の手段としても人気があり、
「先生構文」と呼ばれる派生表現群を生み出すなど、今も進化を続けています。
先生俺しにたいんですよの元ネタとは?ネットで広まった理由を徹底解説【まとめ】
- 元ネタは『ボーイズ・オン・ザ・ラン』説が有力だが確証はない
- ネット上で自然発生的に生まれた構文ミームの可能性が高い
- 感情の落差をオチにするスタイルが人気となり拡散
- 「先生、俺○○したいんすよ」など多数の派生が誕生
- 現在はツイート文学的な文化の一部として定着している