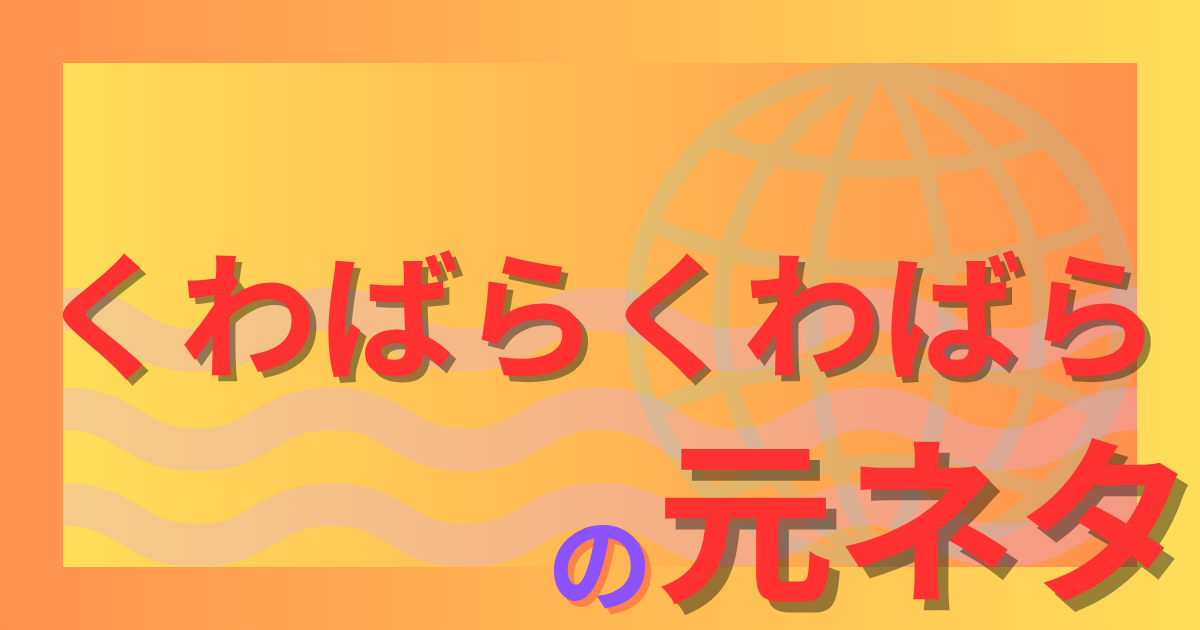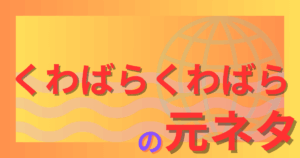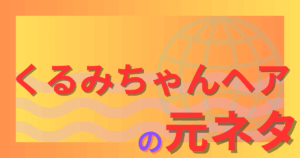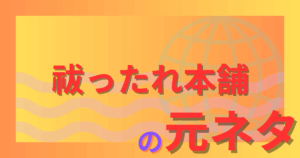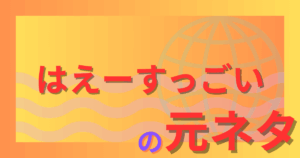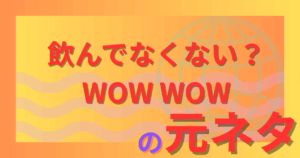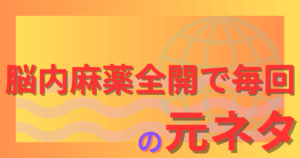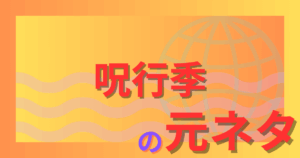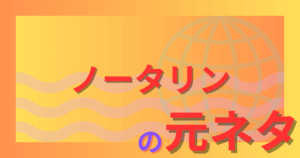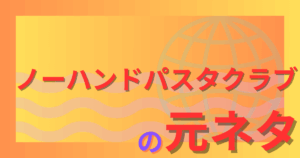雷が鳴ると「くわばらくわばら」と唱える――この言葉は昔から怖いことを避けるためのおまじないとして親しまれてきました。
一方で、「今ではもう死語なのでは?」と思う人もいるかもしれません。
実は、「くわばらくわばら」には日本人の“災いを遠ざける願い”が込められており、「つるかめつるかめ」のように不吉を払う縁起言葉と深くつながっているのです。
この記事では、「くわばらくわばら」の意味や由来、怖いと言われる理由、そして現代でも通じる日本的なおまじないの魅力をわかりやすく解説します。
くわばらくわばらの元ネタとは?雷を避けるおまじないの由来
- くわばらくわばらの意味とは?
- 雷除けとして使われた理由
- くわばらくわばらの語源にまつわる説
- くわばらくわばらが「怖い」と言われる理由
くわばらくわばらの意味とは?
「くわばらくわばら(桑原桑原)」とは、雷が鳴るときに唱える雷除けの呪文です。
「桑原」という地名に雷が落ちなかったという伝説から、「くわばらくわばら」と唱えると災難を避けられると信じられてきました。
雷除けとして使われた理由
古代では雷を「神の怒り」や「祟り」と捉え、人々は雷鳴に強い恐怖を感じていました。
その中で「くわばらくわばら」と唱えることで、雷神に“ここは安全な場所だ”と伝え、落雷を避けるという信仰が生まれました。
くわばらくわばらの語源にまつわる説
語源にはいくつかの有力な説があります。
- 菅原道真説:道真の怨霊が雷を落としたが、彼の領地「桑原」だけは雷を免れた。
- 桑の木説:雷神は桑の木を嫌うという民間信仰。
- 民話説:雷の子どもが井戸に落ち、助けられた恩返しとして「桑原には雷を落とさない」と誓った。
どの説も、「桑原」という名に**“災いを遠ざける力”**があるとされている点が共通しています。
くわばらくわばらが「怖い」と言われる理由
「くわばらくわばら」は、怨霊や祟りに対する恐れが生んだ言葉でもあります。
平安時代、人々は菅原道真の怒りが都に雷を落とすと信じ、「くわばらくわばら」と唱えて怨霊を鎮めようとしました。
つまりこの言葉は、**“怖いことが起きないように願う呪文”**として広まったのです。
現代でも、怖い話や不吉な話題のあとに冗談まじりで唱えられることがあります。
くわばらくわばらの元ネタに関する伝承や逸話
- 菅原道真と桑原の地名説
- 雷神が井戸に落ちた民話説
- 桑の木を嫌う雷神の伝承
- 養蚕と桑畑を守る祈りの言葉
- 現代まで残る「くわばらくわばら」の使われ方
- 「つるかめつるかめ」との共通点――不吉を避ける日本古来のおまじない
- 「くわばらくわばら」は死語なの?今も残る文化的な意味
菅原道真と桑原の地名説
最も有名な説が「菅原道真の祟り」説です。
道真が亡くなった後、都では落雷が続き、人々は「これは道真公の怒りだ」と恐れました。
しかし、彼の領地であった「桑原」には雷が落ちなかったため、「桑原には守りの力がある」と言い伝えられたのです。
雷神が井戸に落ちた民話説
雷の子どもが井戸に落ちてしまい、村人に助けられたという伝説があります。
雷神は感謝して「桑原にはもう雷を落とさない」と約束した――それが「くわばらくわばら」の由来とされています。
桑の木を嫌う雷神の伝承
雷神は桑の木を嫌うという言い伝えがあり、「桑原」と唱えることは雷を遠ざける呪言でもありました。
桑は生命力の象徴であり、自然と信仰が結びついた例といえます。
養蚕と桑畑を守る祈りの言葉
昔の日本では、桑畑は生活の基盤でした。
農民たちは雷による火災や害虫を恐れ、「桑原に雷が落ちませんように」と願いを込めて唱えたと伝えられます。
「くわばらくわばら」は自然への畏敬と祈りの象徴でもあったのです。
現代まで残る「くわばらくわばら」の使われ方
今日では実際に雷除けとして使う人は少ないですが、「縁起直し」や「怖い話のあと」に使われることがあります。
たとえば、「それ以上言うと怖いから、くわばらくわばら」といった使い方です。
「つるかめつるかめ」との共通点――不吉を避ける日本古来のおまじない
「つるかめつるかめ」は「鶴は千年、亀は万年」という長寿の象徴に由来し、不吉を払う言葉として用いられてきました。
どちらも災いを遠ざける日本的な言葉であり、**“心を落ち着かせる呪文”**として共通しています。
「くわばらくわばら」は死語なの?今も残る文化的な意味
現代の若者にはあまり馴染みがなく「死語」と思われがちですが、文学・落語・ドラマなどで今も使われています。
“古き良き日本語”の響きとして、言霊文化を伝える象徴的な存在と言えるでしょう。
くわばらくわばらの元ネタ・怖い・死語・つるかめつるかめまとめ
- 「くわばらくわばら」は雷除けのおまじないとして広まった。
- 語源は菅原道真の祟り伝説や桑の木信仰など複数存在する。
- 「怖い」と言われるのは、怨霊や自然災害を鎮める呪文だったから。
- 「つるかめつるかめ」も同様に、不吉を避ける日本的なおまじない。
- 現代では死語気味だが、文化的価値の高い日本語表現として残っている。