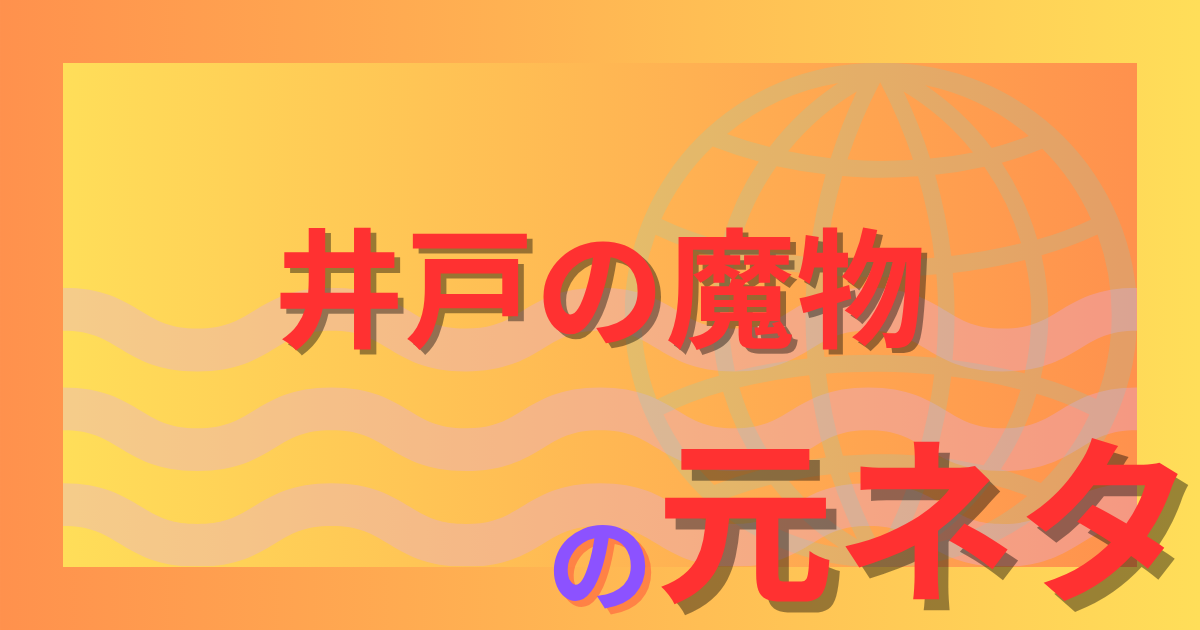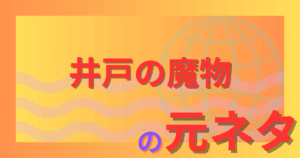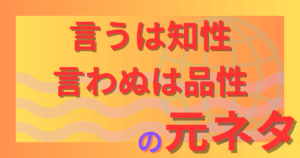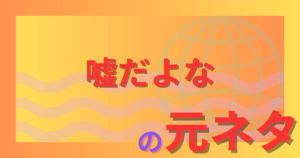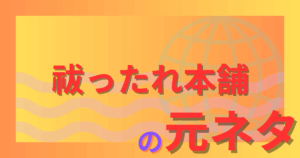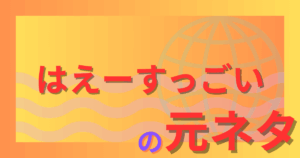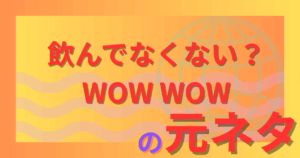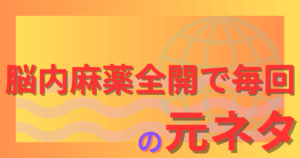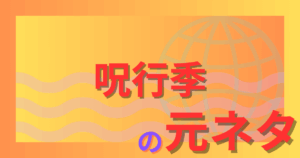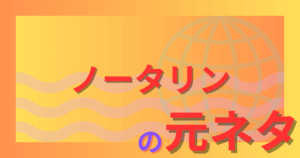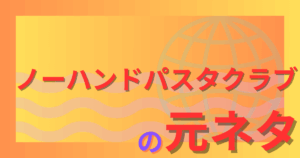井戸の魔物の元ネタとは?
- 芸人・佐久間一行のネタが元祖?
- 勇者ヨシヒコで登場した「井戸の怪人」
- ドラクエの「いどまじん」との関連
- 日本の怪談や妖怪伝承とのつながり
芸人・佐久間一行のネタが元祖?
「井戸の魔物」が話題になるとき、必ずと言っていいほど名前が挙がるのが芸人・佐久間一行さんです。佐久間さんは「井戸のお化け」というネタを持っており、R-1グランプリでも披露しました。コミカルに井戸から現れて歌い踊るスタイルで、観客に強烈な印象を与えました。この芸人ネタが広まり、のちに「井戸の魔物」というフレーズがネットやSNSで使われるようになったと考えられます。
勇者ヨシヒコで登場した「井戸の怪人」
さらに佐久間さんは、ドラマ『勇者ヨシヒコと悪霊の鍵』第5話で「井戸の怪人」として出演。番組公式サイトにもキャラクターとして掲載されており、「井戸をネタにひたすら歌い踊るだけの怪人」と説明されています。これにより、芸人のネタがドラマを通して多くの視聴者に届き、ネットで「井戸の魔物」として認知が広がったのです。
ドラクエの「いどまじん」との関連
一方で、ゲーム『ドラゴンクエストVI』に登場するモンスター「いどまじん」も「井戸に棲む魔物」のイメージを形づくった存在とされています。井戸を調べると出てくる敵キャラという仕掛けが印象的で、ドラクエを遊んだ世代にとっては「井戸=魔物」という図式が自然に結びつきました。
日本の怪談や妖怪伝承とのつながり
さらに遡れば、日本各地には「井戸には怪異が棲む」という伝承が多く残っています。井戸を覗いた人が引き込まれる話や、水底から妖怪が現れる話は古来より語られており、井戸は「異界の入口」として恐れられてきました。この伝承も「井戸の魔物」という言葉の背景に影響を与えているといえるでしょう。
井戸の魔物が広まったきっかけ
- ネットやSNSで拡散された理由
- 芸人ネタと動画文化の相性の良さ
- ミーム化して定着した流れ
ネットやSNSで拡散された理由
「井戸の魔物」が急速に広まった背景には、TikTokやYouTubeといった動画文化の存在があります。佐久間一行さんのネタや『勇者ヨシヒコ』のシーンが切り取られ、ショート動画やミームとして拡散されたのです。
芸人ネタと動画文化の相性の良さ
佐久間さんの芸風は一人で舞台を作り上げるスタイルで、短時間でもインパクトが強いのが特徴です。井戸から登場するだけのシンプルな構成が逆にウケを呼び、ネット動画との相性も抜群でした。これが「井戸の魔物」というフレーズを覚えやすく、真似されやすいものにしたと考えられます。
ミーム化して定着した流れ
SNSでは「井戸の魔物」が「正体不明で不気味なもの」や「唐突に現れるネタ」として二次的に使われるようになり、言葉だけが独り歩きする形でミーム化しました。今では元の芸人ネタを知らない世代でも、自然に使うネットスラングになっています。
井戸の魔物と他作品のつながり
- ホラー作品で描かれる井戸の恐怖
- 海外の伝承にも見られる「井戸の怪物」
- 文化的に井戸が持つ象徴性
ホラー作品で描かれる井戸の恐怖
井戸はホラーの定番モチーフでもあります。特に映画『リング』では貞子が井戸から現れる描写が強烈で、井戸と恐怖を結びつけるイメージを決定づけました。こうしたホラー作品の影響も「井戸の魔物」という表現を補強しています。
海外の伝承にも見られる「井戸の怪物」
ヨーロッパの伝承では「井戸を覗くと精霊に魂を奪われる」といった話があり、日本と同じように井戸を異界の象徴とする文化が存在します。世界的に見ても、井戸は単なる生活用水の場ではなく、神秘と恐怖の対象だったことがわかります。
文化的に井戸が持つ象徴性
井戸は地上と地下をつなぐ存在として、人々に「境界」を意識させてきました。そこに怪物や妖怪を結びつけるのは自然な流れであり、「井戸の魔物」が現代にまで語られる背景には、この文化的象徴があるのです。
井戸の魔物の元ネタは?まとめ
- 芸人・佐久間一行のネタが大元で流行のきっかけ
- **勇者ヨシヒコでの「井戸の怪人」**出演で一気に広まった
- **ドラクエの「いどまじん」**などゲームの影響も強い
- 日本の怪談伝承やホラー作品が背景にある
- ネット動画文化と相性が良く、ミーム化して定着した