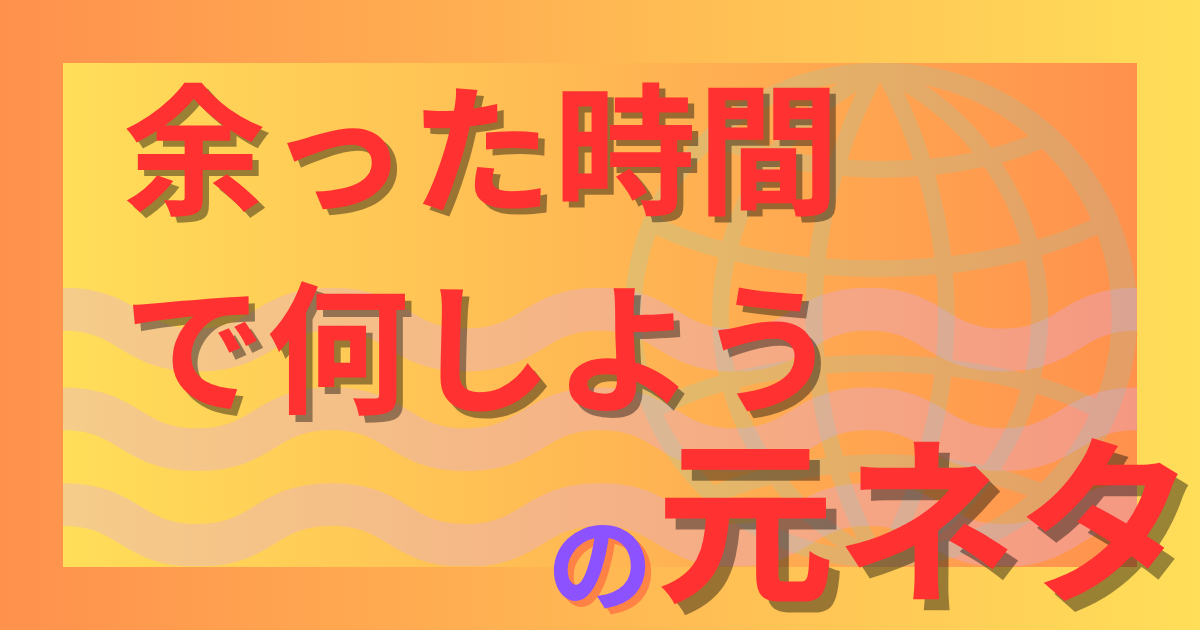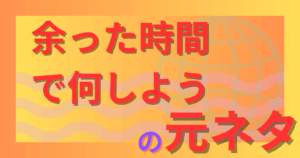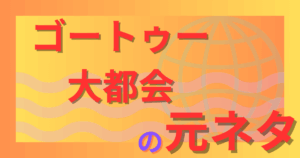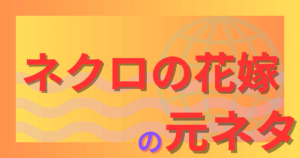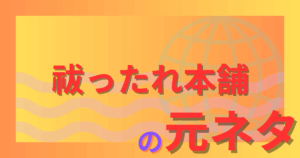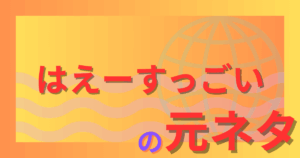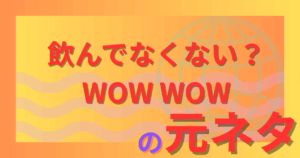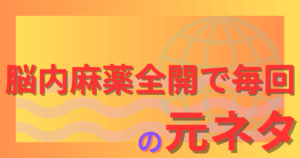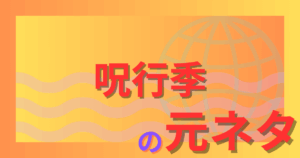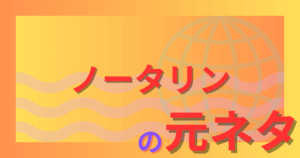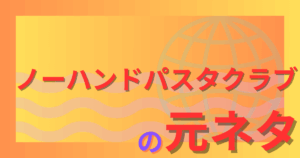ネットでよく耳にする「余った時間で何しよう」というフレーズ。実はこの言葉は、儒烏風亭らでんさんの配信から生まれた元ネタであり、その後「まいたけダンス」として大きなブームを巻き起こしました。キャッチーなリズムとユーモアあふれる歌詞が若者を中心に広がり、TikTokやYouTubeショートで爆発的に拡散されています。
この記事では「余った時間で何しよう」の元ネタや流行のきっかけ、まいたけダンスとの関係や人気の理由について詳しく解説します。
余った時間で何しようの元ネタとは?流行のきっかけ
- 余った時間で何しようの元ネタの起源とは?
- いつ頃から流行った?
- まいたけダンスは誰が考えた?
余った時間で何しようの元ネタの起源とは?
「余った時間で何しよう?」というフレーズの元ネタは、VTuberの儒烏風亭らでんさんの配信中に披露された即興の歌が起源です。らでんさんがリズミカルに「余った時間で何しよう? あ、それ~」と歌ったことがきっかけで、コミカルかつ耳に残るフレーズとして注目を集めました。視聴者がその部分を切り抜き動画として投稿したことで一気に拡散し、ネットミームとして定着しました。
いつ頃から流行った?
このフレーズが広まり始めたのは2023年後半から2024年にかけてです。特に「TikTok」や「YouTubeショート」などの短尺動画プラットフォームで使用されることで急速に拡大しました。キャッチーなメロディーと誰でも真似できる振り付けの親しみやすさが、若者を中心にブームとなった大きな理由です。
まいたけダンスは誰が考えた?
まいたけダンスを最初に生み出したのは、VTuber儒烏風亭らでんさんです。配信中の即興ソングをきっかけにフレーズと振り付けが誕生し、視聴者の切り抜きによって「まいたけダンス」と名付けられ広がっていきました。
余った時間で何しようの元ネタはまいたけダンス?広がりと人気の理由
- まいたけダンスの内容とは?
- 儒烏風亭らでんとの関係
- 余った時間で何しようがバズった理由
- まいたけグルグルとはどういう意味?
- まいたけぐるぐるの中の人は誰?
まいたけダンスの内容とは?
「余った時間で何しよう?」の後に続くのが「まいたけ まいたけ ぐるぐるぐるぐる…」という歌詞と動きを組み合わせたまいたけダンスです。手を回すようなジェスチャーとリズムに合わせた簡単な振り付けが特徴で、誰でも覚えやすく参加しやすい点が人気につながりました。
儒烏風亭らでんとの関係
このダンスが話題になったのは、儒烏風亭らでんさんのキャラクター性と歌い方の独特さが大きく影響しています。配信内で生まれた一発ネタが、ファンによる切り抜きや二次創作を経て「まいたけダンス」という形で広がったのです。まさに、配信者とファンの相互作用から生まれたネット文化の一例といえます。
余った時間で何しようがバズった理由
このフレーズとダンスが爆発的に広がった理由は、シンプルで真似しやすいリズム感、ユーモアあふれる歌詞、そして動画映えする振り付けの三拍子が揃っていたからです。また、TikTokなどの拡散力が強いSNSに相性が良かった点も見逃せません。短時間で見て楽しめるだけでなく、友達と一緒に真似して撮影する「参加型コンテンツ」として定着しました。
まいたけグルグルとはどういう意味?
「まいたけグルグル」に特別な意味はなく、響きとリズム感を重視した言葉遊びです。まいたけという身近なキノコの名前と「ぐるぐる」という動きを示す言葉を合わせることで、耳に残るユーモラスな表現になっています。意味がないのに中毒性がある点が、拡散力を高めた大きな要因です。
まいたけぐるぐるの中の人は誰?
「まいたけぐるぐる」を歌ったのは、元ネタを作った儒烏風亭らでんさん本人です。派生した動画では他のVTuberや一般の投稿者が真似して広まりましたが、オリジナルはらでんさんの配信から始まりました。
余った時間で何しようの元ネタは?まとめ
- 「余った時間で何しよう」の元ネタはVTuber儒烏風亭らでんさんの配信中の即興ソング
- 2023年後半から2024年にかけてSNSで拡散され流行
- 「まいたけダンス」として振り付け付きで定着
- まいたけグルグルは意味のない言葉遊びで中毒性抜群
- 中の人は儒烏風亭らでんさん本人であり、派生動画でさらに広がった